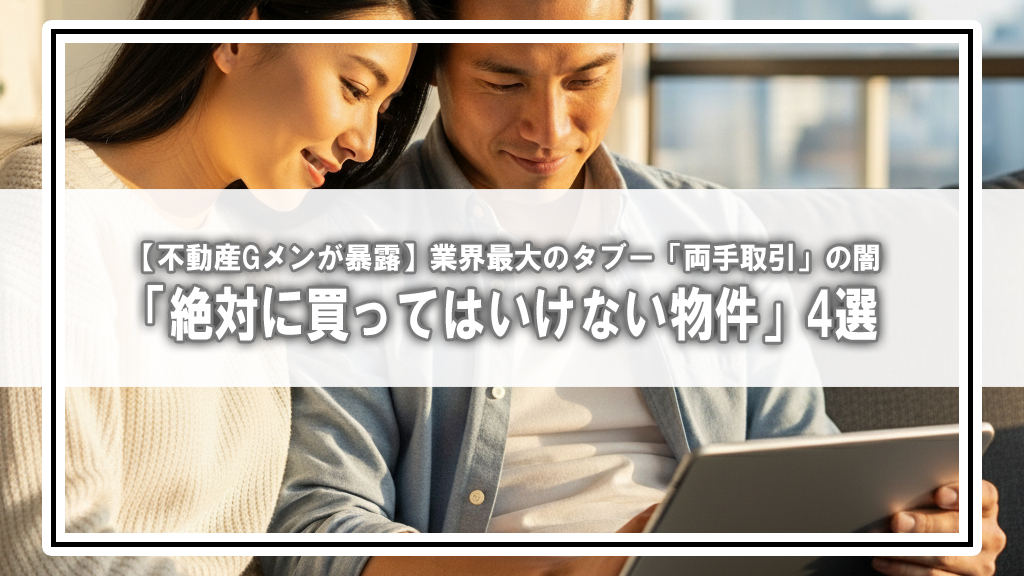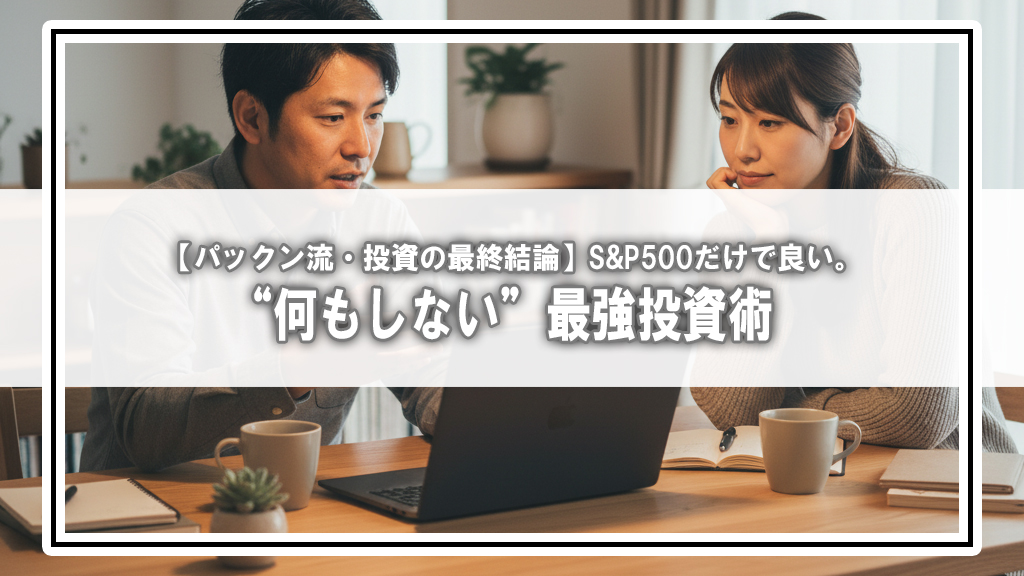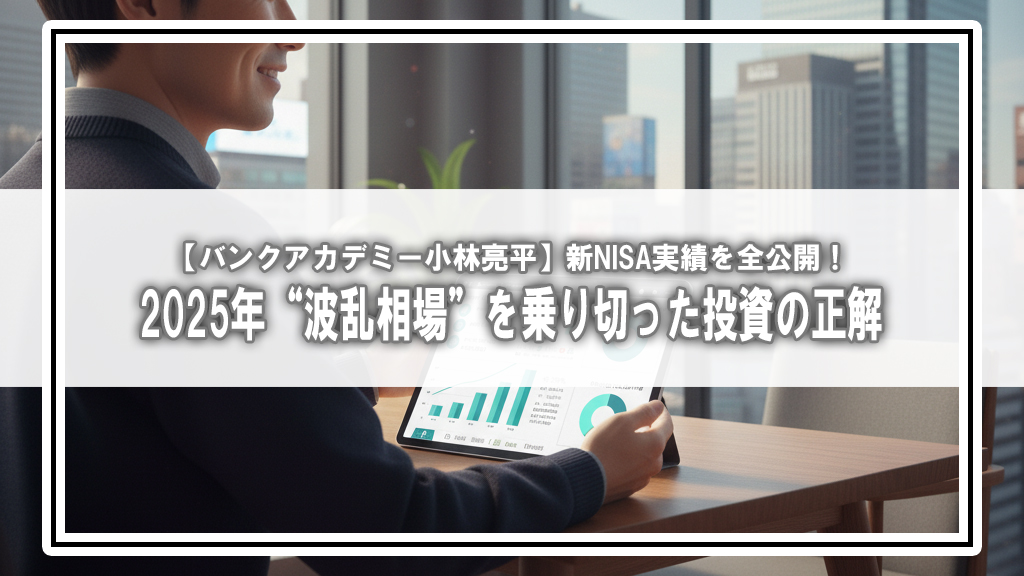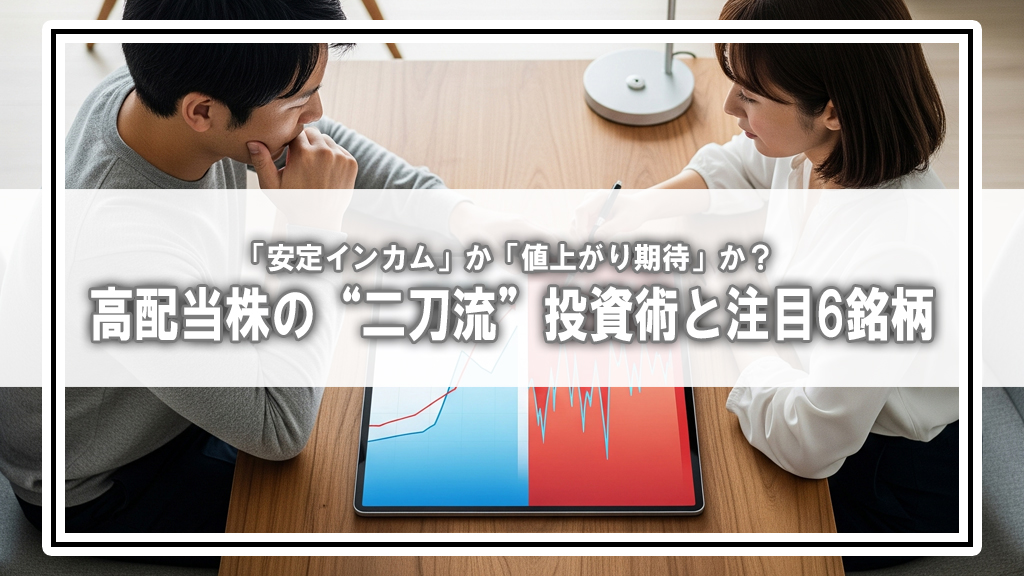【リアル正直不動産】原案者・夏原武が高橋対談で暴露!業界の“本当の闇”と、絶対に買ってはいけない物件【ReHacQ動画まとめ】
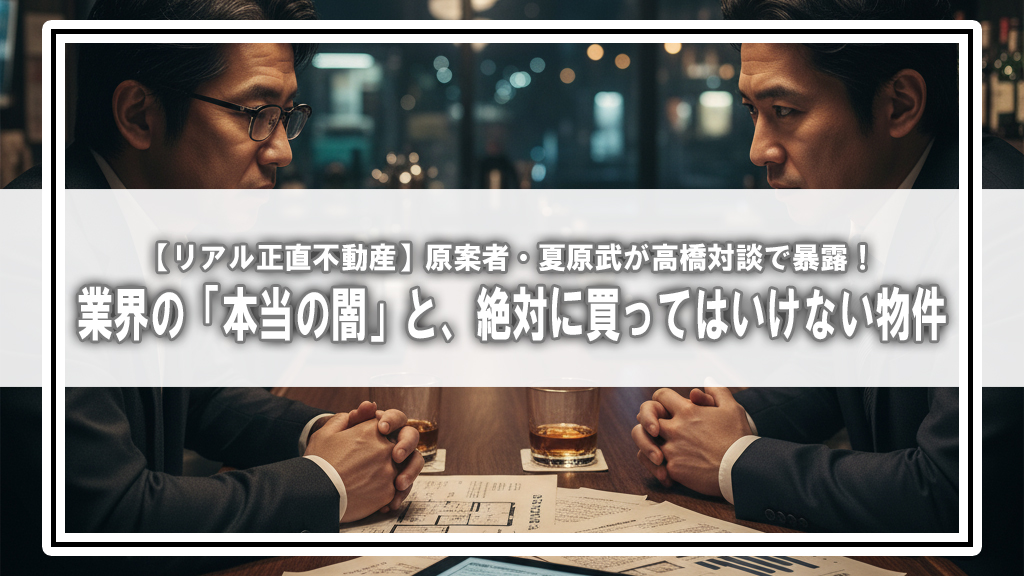
「マイホーム購入」や「不動産投資」──。それは、人生における、最も大きな決断の一つです。 しかし、その華やかな世界の裏側には、一般消費者が決して知ることのない、根深い“闇が広がっているとしたら…?
あの人気ドラマ『正直不動産』の原案者・夏原武さんが、ついに重い口を開きました。
この記事では、人気YouTube番組「ReHacQ」で、業界の裏側を知り尽くした彼が赤裸々に語った、衝撃の“内部告発”を徹底解説します。
日本の不動産取引を歪める諸悪の根源「両手取引」の実態から、プロが断言する「買った瞬間に負債と化す、絶対に買ってはいけない物件」の具体的な特徴まで。
これは、家を買う、借りる、投資する、すべての人が、巨額の損失から身を守るために知っておくべき、不都合な真実の物語です。

動画で紹介された内容を、投資初心者でも分かるようにまとめました。
出演者:夏原武/弥田有三/高橋弘樹
取材協力:株式会社みなと相続コンシェル
注意:投資は自己責任でお願いします。この記事は動画の内容をまとめたものであり、投資を推奨するものではありません。
不動産業界の闇
番組冒頭で夏原さんと弥田さんが指摘したのは、不動産取引における「情報の非対称性」「囲い込み」が、業界の闇の根源であるということです。
不動産業界最大の闇「情報の非対称性」
不動産取引は「プロと素人の戦い」
夏原さんと弥田さんがまず強調するのは、不動産取引が「プロ(不動産会社)と素人(一般消費者)の戦い」であるということです。
- 素人の情報リテラシーの低さ
- 不動産の売買は、人生でそう何度も経験することではありません。そのため、私たちは不動産に関する専門知識や市場のリアルな情報を持たない「情報弱者」になりがちです。
- プロは「一見さん」と認識
- 不動産会社からすれば、一般の顧客は「一見さん」です。リピートが少ないため、「騙してもいいか」という意識が生まれやすい構造だと、動画では指摘されています。
この情報格差(情報の非対称性)こそが、不動産業界の闇の根源であり、消費者が損をする最大の要因であると語られます。
業界最大のタブー「両手取引」と「囲い込み」の仕組み
この「情報の非対称性」を悪用する、業界最大のタブーが「両手取引」と「囲い込み」です。
「両手取引」とは?
- 普通の取引(片手取引)
- 通常、不動産売買では「売主側の仲介会社」と「買主側の仲介会社」がそれぞれ存在し、手数料はそれぞれの顧客から受け取ります。
- 両手取引の仕組み
- しかし、「両手取引」では、一つの不動産会社が売主と買主の双方から仲介手数料を受け取ります。 これにより、不動産会社は「売主から3%+買主から3%」といった形で、手数料を倍額稼ぐことができます。
「囲い込み」とは?
両手取引を成立させるために、不動産会社が行うのが「囲い込み」です。
- 情報の独占
- 売主から物件の売却依頼を受けた不動産会社が、その物件情報を他の不動産会社に意図的に公開しない、あるいは公開を遅らせる行為です。 SUUMOやHOME’Sのようなポータルサイトに出しても、他の会社からの買い付け申し込みは「受け付けない」という対応を取ります。
- 売主・買主が知らないうちに損をする
- 売主の損失
他の不動産会社が持つ、より高く買ってくれるかもしれない買主と出会う機会を奪われます。結果として、本来3,000万円で売れるはずの物件が、2,800万円など安い価格で売却されてしまうことになります。 - 買主の損失
市場にあるはずの物件情報が隠されてしまうため、希望の条件に合う物件に出会う機会を失います。 結局、業者側が両手取引を狙っている物件の中から選ばざるを得なくなり、適正価格より高く買わされてしまうこともあります。
- 売主の損失
- なぜ横行するのか?
- 両手取引は、アメリカなど多くの国では法律で禁止されていますが、日本では合法です。これが、不動産価格が不透明で、消費者が損をしやすい構造の根源にあると、動画では断言されています。
「2回転」という悪質な手口
さらに悪質な手口として「2回転」が紹介されました。 これは、売主を弱気にさせ、「この値段ではなかなか売れませんね」などと言って、知り合いの不動産業者や工務店に安く物件を買い取らせる手口です。
その後、買い取った業者がリノベーションを施し、元々依頼を受けていた不動産会社が、その物件を高く再販します。 これにより、最初に依頼を受けた不動産会社は、安く買わせたことへの「担当者ボーナス」を受け取るだけでなく、再販時にも仲介手数料を得るという、1つの物件から何度も利益を吸い上げる構図が生まれます。
賃貸物件にも潜む闇
賃貸契約は一見すると公平に見えますが、ここにも消費者が損をしやすい「闇」があると解説されました。
賃貸初期費用に潜む「ごまかし」の罠
多くの人が引っ越しで経験する「初期費用」。その内訳には、実は疑わしい項目が少なくない、と動画では指摘されています。
- 「鍵交換費」の嘘
- 「入居時には必ず鍵を交換します」と言われ、数万円を請求される鍵交換費。しかし、実際には鍵の清掃や研磨をするだけで交換していないケースや、そもそも交換の必要がないのに請求されているケースが横行していると言います。
- 「消毒費」「消臭費」のカラクリ
- 「入居前の消毒・消臭が必須です」と請求されるこれらの費用も、実態は数千円のスプレーを撒くだけで、数万円が請求されることが珍しくありません。これは、実費よりもはるかに高額な「ごまかし」だ、と夏原さんは断言します。
- なぜこんな費用が請求されるのか?
- 不動産会社が受け取れる仲介手数料には上限(家賃の1ヶ月分+消費税)があります。そのため、この上限では儲けが足りないと感じる会社が、別の名目で利益を上乗せしようと、こうした費用を請求するのです。
「仲介手数料無料」の裏側と”不人気物件”への誘導
「仲介手数料無料」は、賃貸を探す人にとって非常に魅力的な言葉です。しかし、その裏側にも、私たちが知るべき仕組みが隠されています。
- オーナーからの「広告料(AD)」
- 仲介手数料が無料の不動産会社は、多くの場合、物件のオーナー(大家さん)から高額な「広告料(AD)」を受け取ることで利益を得ています。
- 「AD」が高い物件の正体
- オーナーが高額なADを払ってでも入居者を見つけたい物件は、多くの場合、立地が悪い、家賃が高い、設備が古いなど、「借り手が見つかりにくい不人気物件」である可能性が高いと、夏原さんは指摘します。
- 「おとり物件」と「巧妙な誘導」
- 「仲介手数料無料」の不動産会社は、当然ながらADが付いている物件を優先的に紹介したがります。
- 「おとり物件」の利用
- ポータルサイトに、実際にはもう入居者が決まっている、あるいは存在しない「安くて魅力的な物件(おとり物件)」を掲載し、顧客を来店させる手口が横行しています。
- 「マインドコントロール」による誘導
- 来店した顧客に対し、巧みな話術で不人気物件のメリットだけを強調したり、「この物件はすぐ埋まりますよ」と焦らせたりして、顧客を儲かる物件へと誘導する「マインドコントロール」のような営業が行われることがあります。
指定される「保証会社」や「火災保険」の罠
仲介手数料以外にも、契約時に注意すべき「見えないコスト」が存在します。
- 「キックバック」目的の指定
- 賃貸契約では、家賃保証会社や火災保険会社が指定されることがよくあります。しかし、仲介手数料が無料の会社では特に、相場よりも割高な会社を指定されるケースがあります。 これは、不動産会社に「キックバック(紹介料)」が入る仕組みになっているためです。顧客は「手数料無料だからお得」と思いきや、知らず知らずのうちに別の名目で余分な費用を払わされています。
- 契約書を隅々までチェック
- 保証会社の費用や火災保険料は、月々の家賃などと異なり、一度払えば終わりなので、つい見落としがちです。しかし、これらの費用も積もり積もれば大きな金額になります。契約書を渡されたら、指定された会社が本当に相場に見合っているか、自分で調べてみるなどの注意が必要です。
投資用不動産に潜む「自己破産の罠」
特に危険だと夏原さんが警鐘を鳴らしたのが、投資用不動産、特にワンルームマンション投資です。
買ってはいけない!「新築ワンルームマンション投資」の闇
「買った瞬間に価値が2〜3割下落する“負動産”」
夏原さんが特に危険だと断言するのが、新築ワンルームマンションへの投資です。
- 甘いセールストークの裏側
- 「節税になる」「生命保険の代わりになる」「老後の年金対策に」といったセールストークで、高収入のサラリーマン層を中心に販売されます。
- 業者の莫大な利益が上乗せ
- しかし、その実態は、販売業者の利益が大幅に乗せられているため、購入した瞬間に、その物件の市場価値が2〜3割も下落するという厳しい現実です。つまり、買った直後から「資産」ではなく「負動産」と化してしまうリスクが極めて高いのです。
年収600万円でローン6,000万円が「自己破産予備軍」
動画では、年収600万円程度のサラリーマンが、安易に6,000万円や8,000万円といった巨額のローンを組んで、複数のワンルームマンションに投資した結果、最終的に自己破産に追い込まれるケースが後を絶たない
巧妙に仕組まれた「利回りの偽装」と「空室リスク」
投資用不動産を魅力的に見せるための、巧妙な「偽装工作」が存在します。
- 「高すぎる表面利回り」のカラクリ
- 「利回り10%!」といった魅力的な数字の裏には、様々なカラクリが隠されています。
- 意図的な「満室偽装」
- 物件を売りやすくするため、オーナー(業者)の息のかかった知人などを一時的に入居させ、見かけ上だけ「満室」に見せる手口があります。
- 高すぎる賃料設定
- その地域の相場からは考えられないような、不自然に高い賃料で入居者を入れることで、利回りを高く見せかけます。
- 入居者の「追い出し」詐欺
- さらに悪質なケースとして、生活保護受給者などを一時的に集めて満室にし、物件を売却後、その入居者が一斉に退去して物件が「全部空室」になるという、組織的な詐欺の手口も語られました。これは、埼玉の不動産屋が東京の業者にやられたという具体例も示されています。
- 見過ごされがちな「本当の空室リスク」
- ワンルームマンションは、入居者の入れ替わりが頻繁に起こるため、「空室期間」が必ず発生します。しかし、初心者はこのリスクを低く見積もりがちです。
- 利回り半減の現実
- 想定していた賃料で借り手が見つからず、1割、2割と家賃を下げざるを得なくなるケースが多々あります。その結果、購入時に提示された利回り10%が、実質的には1%にも満たない、あるいはマイナス(ローン返済額が家賃収入を上回る)になることも珍しくありません。
自己破産へと導く「追い貸し」と「運転資金の欠如」
ローンを組んで投資用不動産を購入する際に、特に注意すべき点が指摘されています。
- 高金利の「投資用ローン」
- 住宅ローンに比べて、投資用ローンは金利が高く設定されています。この高金利を賄えるだけの収益を物件が生み出せるか、非常にシビアな判断が必要です。
- 「運転資金」の重要性
- 空室が続いたり、賃料を下げざるを得なかったりした場合、その間のローン返済や管理費・修繕積立金を自己資金で賄う「運転資金」が必須です。しかし、多くの初心者はフルローンで物件を購入するため、この運転資金が不足しがちです。
- 「塩漬け」からの自己破産
- 一度「負動産」と化した物件は、売ろうとしても買い手がつかず、「塩漬け」状態になります。月々マイナスが出続ける状況で運転資金も尽きれば、最終的には自己破産へと追い込まれてしまうのです。
不動産取引で「損をしない」ための鉄則
夏原さんと弥田さんは、これらの闇から身を守るための具体的な方法を伝授しました。
基本の基本!「知識武装」と「疑う心」が最大の防御
夏原さんと弥田さんが最も強調するのは、不動産取引は「プロ(肉食獣)と素人(草食動物)の戦い」であるという認識を持つことです。
- 知識武装の徹底
- 「なんとなく」で進めるのは絶対にやめましょう。不動産に関する基本的な知識をつけ、業者の話が本当かどうかを自分で判断できる力を養うことが不可欠です。夏原さんの著書『正直不動産』を「新入社員の必読書」としている会社もあるほど、業界の実態が詰まっています。
- 「セミナーには行かない」
- 「儲かる」と煽るための不動産投資セミナーは、ほとんどが「サクラ」であり、行くべきではないと断言されました。甘い言葉で誘導され、高額な商品を買わされるリスクが非常に高いです。
失敗しない「不動産会社選び」と「営業担当者選び」
不動産取引の成否は、パートナー選びで決まると言っても過言ではありません。
- 「大手だから安心」は幻想
- ネット検索やCMで有名な大手だからといって、必ずしも信用できるわけではありません。大手不動産会社も「両手取引」を前提としていることが多く、必ずしも顧客の利益を最優先しているとは限らないと警鐘が鳴らされます。
- 「信頼できる人」を見つける
- 最も重要なのは、会社選びよりも「営業担当者選び」です。口コミや、実際に取引した人の声を聞いて、「誠実な営業マン」を見つけることが何よりも重要です。
- 良い営業担当者の見分け方
- こちらの話をちゃんと聞いてくれる。
- 質問にきちんと答えてくれる。
(聞かれないことは教えないのが基本スタイルのため) - 自分の都合でしょっちゅう連絡してこない。
(契約を急がせない)
- 「相見積もり」と「競わせる」姿勢
- 物件の売却時も購入時も、複数の不動産会社から査定や提案を受け、競争させることが大切です。弥田さんが提供する「代理人売却サービス」のように、プロがレフェリー役となって複数の業者を競わせる仕組みを利用するのも賢明な選択です。
冷静な判断を!「即決NG」と「現場確認」
不動産取引は、高額なだけに焦りや感情的な判断が命取りになります。
- 「即決」は絶対にしない
- 「今決めないと他の客に取られる!」といった営業トークは、詐欺師の常套手段です。どんなに魅力的な物件でも、その場で契約せず、必ず一度持ち帰って冷静に考える時間を取りましょう。
- 「サクラ」の手口
- 「今、仮予約が入りそうなので…」といった電話は、実際にはサクラを使っている可能性が高いです。
- 「現場」を自分の足で確認する
- ポータルサイトの情報だけを信じてはいけません。投資用物件であれ賃貸であれ、必ず現地周辺を自分の足で歩き、地元の人に話を聞くなどして、ポータルサイトには載っていないリアルな情報を集めましょう。
- (例:「このアパートは引っ越しが多い」「周辺の家賃相場は本当にそのくらいか」など)
- ポータルサイトの情報だけを信じてはいけません。投資用物件であれ賃貸であれ、必ず現地周辺を自分の足で歩き、地元の人に話を聞くなどして、ポータルサイトには載っていないリアルな情報を集めましょう。
- 「ボイスレコーダー」の活用も
- 営業担当者との会話は、可能であればボイスレコーダーで記録しておくことも有効です。言った言わないのトラブルを避けることができます。
賃貸契約時の「見えないコスト」にも注意
賃貸物件の契約時にも、見落としがちな費用や、巧妙な誘導が潜んでいます。
- 初期費用に注意
- 「鍵交換費」「消毒費」「消臭費」など、実際にはほとんど行われていないサービスや、実費よりはるかに高額な費用を請求されることがあります。
- 指定される「保証会社」や「火災保険」
- 仲介手数料が無料の会社では特に、指定される保証会社や火災保険が、相場よりも割高なケースがあります。これは不動産会社に「キックバック」が入る仕組みになっているためです。
不動産営業に潜む「闇の誘惑」
不動産会社の一部の営業マンは、目先の利益を追求するために、モラルに反する手口を使うことがあります。
- 「担当者ボーナス(担ボー)」という裏金
- 物件のオーナーが、仲介手数料とは別に、営業マン個人に「この物件を決めてくれたら〇〇万円払う」という「裏金」を渡すことがあります。これにより、営業マンは顧客の利益よりも自分のボーナスを優先し、本来の価値よりも安く物件を売らせたり、高く買わせたりする誘導を行うリスクがあります。
- 数百万単位の裏金も
- 売買では100万円単位の「担ボー」が発生することもあり、フェラーリを買う営業マンもいると語られます。これは脱税の温床になる可能性も指摘されています。
弥田氏の事業「みなと相続コンシェル」の全貌
弥田さんが代表を務める「みなと相続コンシェル」は、もともと「AI相続」という相続税申告書作成プラットフォームの運営からスタートしました。しかし、その事業を通じて、新たな社会課題に直面し、それを解決するための革新的なサービスへと発展させていきました。
AI相続
- 事業内容
- 相続税申告を、税理士に依頼せずとも自分で申告書を作成できるソフトを提供しています。年間5,000件もの利用があり、これは国内最大手の税理士法人の受任数に匹敵するほどです。
- 社会課題の解決
- 複雑で専門知識が必要な相続税申告を、一般の人が手軽に、かつ低コストで行えるようにすることで、相続における情報格差を解消しています。
不動産代理人売却サービス
「AI相続」のユーザーから、相続した実家の売却相談が多く寄せられる中で、弥田さんは不動産売却市場の「情報の非対称性」と「囲い込み」という闇を痛感します。そこで生まれたのが、この画期的なサービスです。
サービス内容の核心
「みなと相続コンシェル」は、自らが仲介業者として「両手取引」を狙うのではなく、売主(顧客)の「レフェリー役」に徹します。その土地に強く、シェアを持つエリアの不動産会社2社を選定し、売主の代わりに査定や販売交渉を行います。
「囲い込み」をなくす仕組み
- 本音の査定を引き出す
- 「みなと相続コンシェル」がプロとして間に立つことで、不動産会社は「本音の査定」を提示せざるを得なくなります。競合他社がいること、そしてレフェリー役がプロであることから、不当に高い査定や、囲い込みを狙った査定は通用しません。
- 2社に販売を競わせる
- 売却依頼を特定の1社に任せるのではなく、選定した2社に販売活動を競わせます。 これにより、不動産会社は囲い込みを行うメリットがなくなり、積極的に買主を探すインセンティブが働きます。
- 売主から手数料は「ゼロ」
- 最も驚くべきは、売主である顧客からは仲介手数料を一切受け取らないことです。収益は、最終的に物件を成約させた不動産会社から「紹介料」という形で得る仕組みになっています。
なぜこのビジネスモデルが成立するのか?
- AI相続からの「確実な売却顧客」
- 「AI相続」のユーザーは、相続税申告という明確な目的で「売る」ことを決めている顧客がほとんどです。そのため、不動産会社にとっては、売却につながる確率が極めて高い「良質な顧客」となります。
- 低コスト運営
- 「みなと相続コンシェル」はレフェリー役に徹するため、物件の現地調査や内覧対応など、不動産会社が通常行う物理的な営業活動にかかるコストが低いです。これにより、低い紹介料でもビジネスが成立します。
- 構造的な問題への挑戦
- 「両手取引」が当たり前の業界で、この「代理人売却」というサービスは異端ですが、夏原さんも「お客さんに損をさせないという大前提が正しい」と評価しています。
不動産業界の未来と「改革」の必要性
現在の不動産業界が抱える問題点に対する、改革の必要性についても議論が及びました。
「宅建士」の地位向上と罰則強化の必要性
問題点:宅建士は「お墨付き」の資格にすぎない?
動画では、宅地建物取引士(宅建士)という資格が、弁護士や司法書士といった他の士業に比べて、社会的な地位や責任の面で課題を抱えていることが指摘されました。
- 弁護士会のような「自治機能」の欠如
- 弁護士には弁護士会があり、不祥事を起こした弁護士には懲戒処分が下されます。しかし、宅建士にはそのような強力な「懲罰規定」や「自治機能」を持つ団体がないのが現状です。
- 「5年に一度居眠りしながら更新」できる資格
- このため、宅建士の資格は「5年に一度、講習を受けて居眠りしながら更新すればいいだけの資格」と揶揄されることもあり、プロとしての高い倫理観や責任感が醸成されにくい構造にあると夏原さんは語ります。
提言:宅建士に「士業」としての誇りを持たせる改革
- 営業は全員宅建士に
- 不動産営業に携わる者は全員、宅建士の資格を必須とすべきだと提言されています。
- 「宅建士会」の設立と懲罰規定
- 弁護士会のように「宅建士会」を設立し、利益相反行為や法律違反をした宅建士には、資格停止や剥奪といった厳しい罰則を設ける仕組みが必要です。これにより、宅建士が自身の資格に誇りを持ち、プロとしての高い職業倫理を持って業務に臨むようになると期待されます。
業界団体が抱える「利権争い」と「足の引っ張り合い」
2つの業界団体が改革を阻む
日本の不動産業界には、大きく分けて2つの業界団体が存在します。
- 全日本不動産協会(ウサギマーク)
- 全国宅地建物取引業協会連合会(ハトマーク)
動画では、この2つの団体が「仲が悪い」ために、業界全体を良くするための改革案が出ても、「片っぽがやっても、もう片っぽがやらない」といった形で利権争いや足の引っ張り合いが起こり、前に進まない現状が指摘されました。
国土交通省の「腰の重さ」
さらに、不動産業界を監督する国土交通省も「腰が重い」ことで有名であり、この業界団体の問題と相まって、外部からの改革の力が働きにくい構造になっていると語られました。
ワンルームマンション業界の「自浄作用」への期待
悪質な営業手法や「負動産」が問題視されてきたワンルームマンション投資業界。しかし、この分野でも変化の兆しが見え始めていると、夏原さんはポジティブな展望を語ります。
- 「新しい都市環境を考える会」
- ワンルームマンション業界の一部では、「このままではいけない」という危機感から、「新しい都市環境を考える会」のような団体が発足し、業界の健全化に向けた動きが活発になっています。
- 期待される変化
- この団体は、ワンルームマンションの価格を適正化したり、販売後の管理運営も責任を持って行ったりすることで、「ちゃんと投資家を育てていく」ような業界を目指していると言います。 これは、消費者が安心して投資できる環境を整えるための、重要な自浄作用と言えるでしょう。
消費者の「リテラシー向上」が最大の改革の原動力
弥田さんは、ご自身の「代理人売却サービス」の経験を通じて、消費者の「知識武装」が、業界を変える最大の力になることを強調します。
- 知識があれば業者は「悪いこと」ができない
- 消費者が不動産の適正価格を知り、正しい知識を持って粘り強く交渉すれば、業者は「囲い込み」などの不公正な手法を使えなくなります。
- 「繰り返しゲーム」としての不動産業界
- プロの不動産会社からすれば、消費者は「一見さん」でも、その消費者が知識を持っていれば、それは「二度と悪い業者とは取引しない」というシグナルになります。これにより、業者側は長期的な信用を失うことを恐れ、より誠実な対応を取るようになります。弥田さんのサービスが「繰り返しゲーム」の環境を作ることで、業者が公正になるように機能している点が紹介されました。
知識は「お守り」、疑う心は「盾」
この対談を通じて、夏原さんと弥田さんが一貫して伝えているのは、不動産取引はプロと素人の情報格差が非常に大きい世界であり、消費者が損をしないためには、徹底した「知識武装」と「疑う心」が不可欠であるということです。
「不動産は人生最大の買い物」だからこそ、後悔しないために、この貴重な”内部告発”を、あなたの「お守り」と「盾」として活用してください。
まとめ
今回は、『正直不動産』の原案者・夏原武さんと、不動産のプロ・弥田有三さんが語った、不動産業界の“本当の闇”と、そこから資産を守るための具体的な方法をご紹介しました。
彼らが一貫して伝えようとしていたのは、不動産取引とは「プロ(肉食獣)と、素人(草食動物)の戦い」である、という厳しい現実です。そして、その戦場で生き残るための、たった一つの、しかし最強の武器があります。
最後に、あなたの資産を守るための「3つの鉄則」を、もう一度心に刻んでください。
- 「知識」で武装せよ
- 「両手取引」「囲い込み」「おとり物件」。業界の常套手段を知ること。それが、あなたがカモにされないための、最低限の「鎧」となります。
- 「疑う心」を盾とせよ
- 「大手だから安心」「手数料無料はお得」「今決めないと無くなる」。営業担当者の甘い言葉を、決して鵜呑みにしてはいけません。常に「なぜ?」と問いかける冷静な視点が、あなたを守る「盾」です。
- 「相見積もり」という剣を振るえ
- 一人の営業担当者に人生を委ねてはいけません。必ず複数の業者を競わせ、比較検討すること。それが、相手に誠実な仕事をさせる、最も強力な「剣」となります。
不動産は、人生最大の買い物です。この記事で得た知識を武器に、後悔のない、賢明な判断を下してください。あなたの資産を守れるのは、あなたしかいないのです。
本記事は動画の内容をまとめたものであり、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。