あなたの実家は「負動産」になる。専門家が語る、2030年からの“空き家地獄”と、東京大暴落のシナリオ【ReHacQ動画まとめ】
おっさん事業主
小さく始めた事業の記録

「株主優待って魅力的だけど、どの株を選べばいいの?」 「長年の投資経験を持つプロは、どんな基準で銘柄を見ているんだろう?」
そんな疑問を持つあなたのために、投資歴41年のレジェンド、”株主優待名人”こと桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル「All About マネー【プロと学ぶお金のキホン】」で、自身の経験から導き出した「買ってはいけない株」と「買うべき株」の明確な基準を語りました。
この記事では、動画の中で語られた桐谷さん流の「投資・株に対する考え方」、具体的な「銘柄例」、そして「初心者が注意すべきアドバイス」を徹底的に解説します。
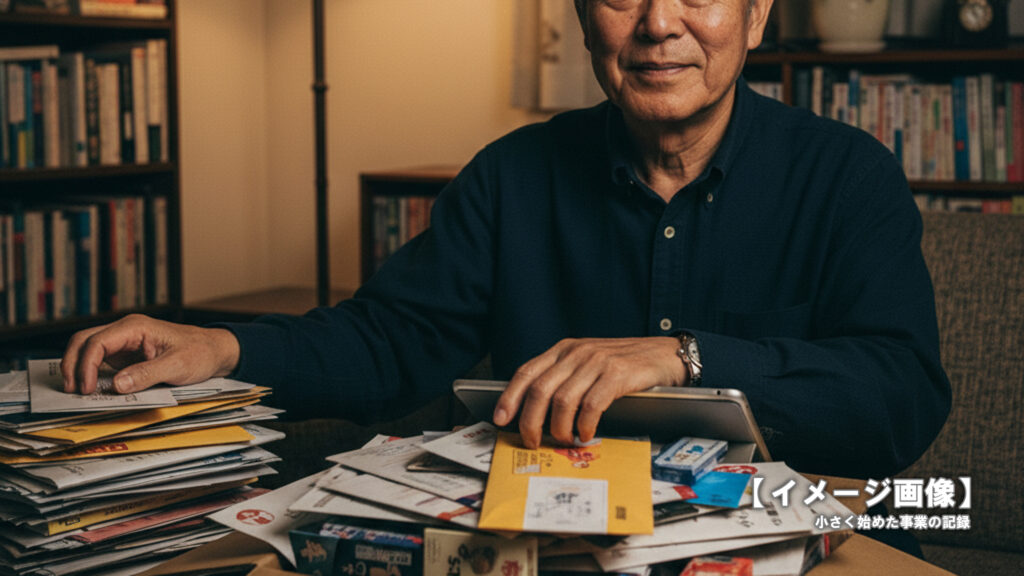
動画で紹介された株や投資のコツを、初心者でも分かるようにまとめました。
注意:投資は自己責任でお願いします。この記事は動画の内容をまとめたものであり、投資を推奨するものではありません。
数々の金融危機や暴落を乗り越えてきた桐谷さん。その経験から導き出された投資の結論は、非常にシンプルかつ力強いものでした。
動画内で語られた、桐谷さんの経験に基づく具体的な銘柄の例や、優待の考え方を見ていきましょう。
桐谷さんの長年の経験から、投資初心者が学ぶべき重要なアドバイスをまとめます。
桐谷さんが41年かけてたどり着いた結論は、「配当と優良な優待が充実した、堅実な企業を、株価が安くなった時に買い、長く持ち続ける」という、王道かつ非常に力強い投資法でした。
このシンプルな原則は、情報が溢れ、市場が混乱しがちな現代において、私たち個人投資家が長期的に資産を築き、優待で人生を豊かにしていくための、最も信頼できる道しるべと言えるでしょう。
本記事は動画の内容をまとめたものであり、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。