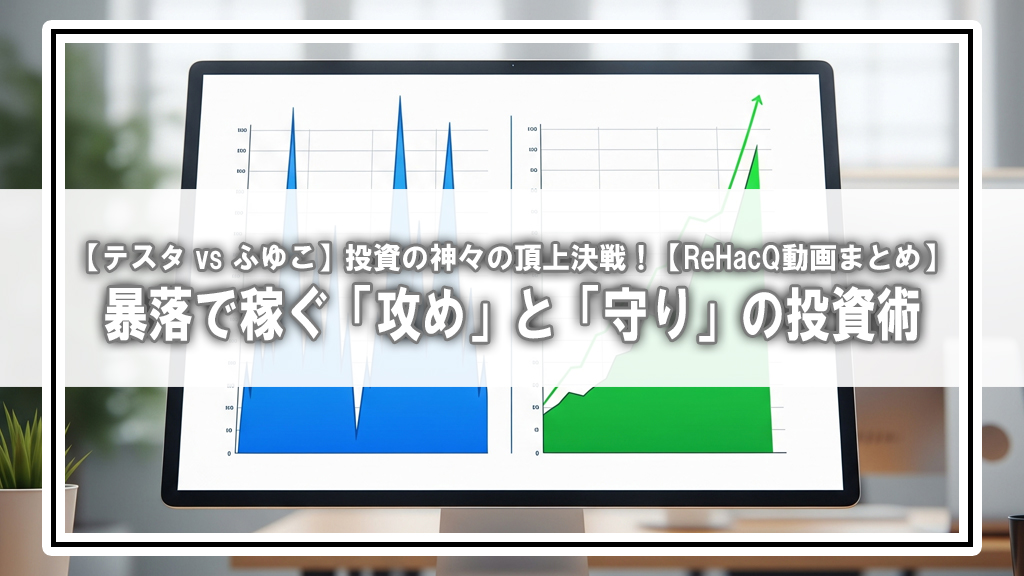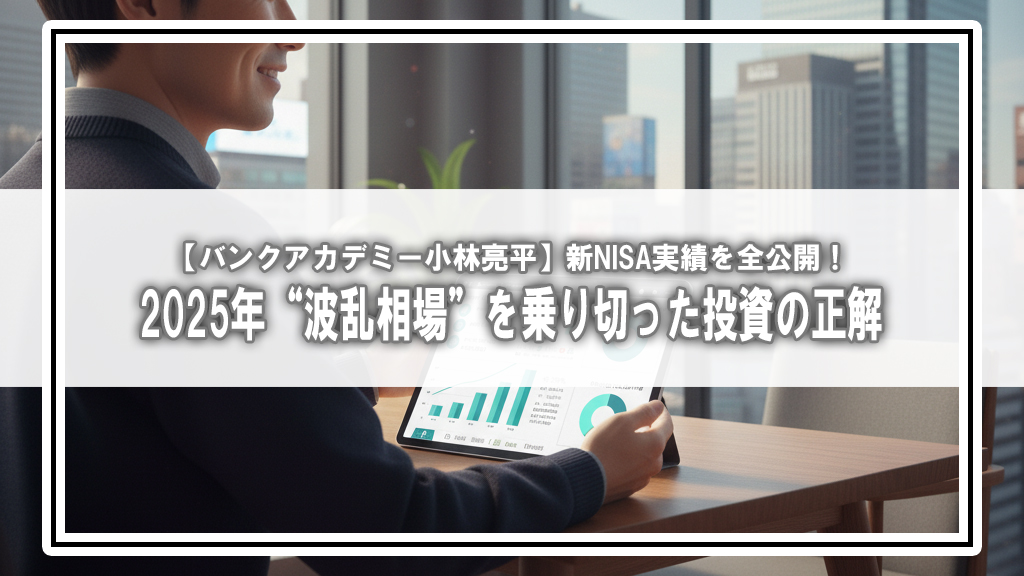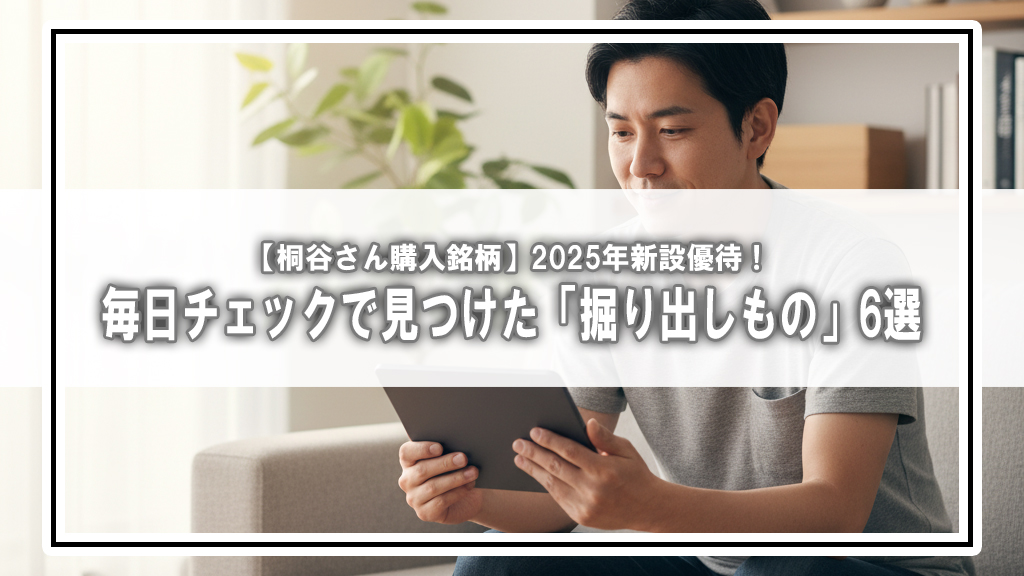あなたの実家は「負動産」になる。専門家が語る、2030年からの“空き家地獄”と、東京大暴落のシナリオ【ReHacQ動画まとめ】
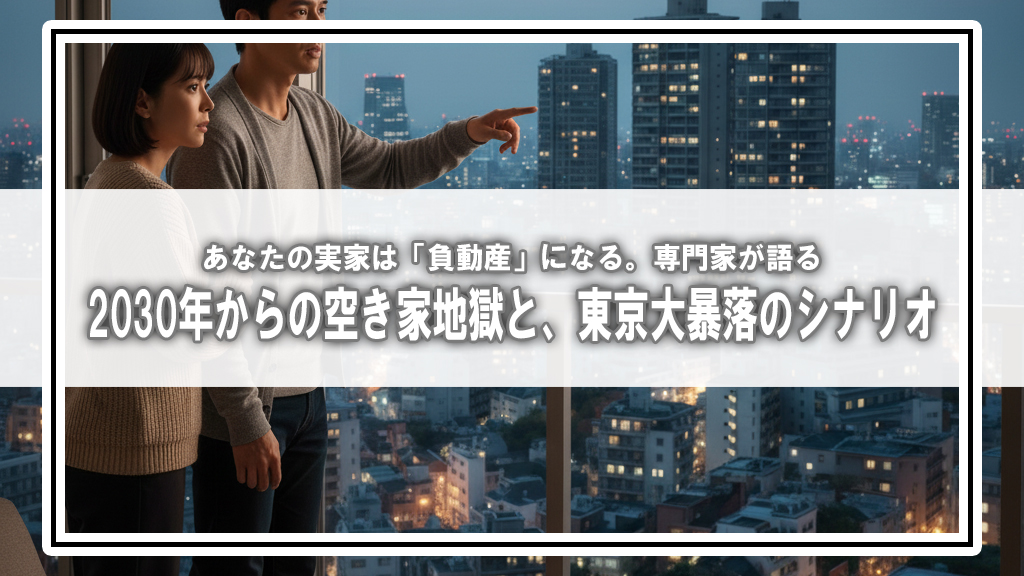
「東京の不動産は、絶対に安全だ」
「親が残してくれた実家は、大切な資産だ」
もし、あなたがそう信じているなら、その“常識”は、数年後に悪夢へと変わるかもしれません。
経済キャスター・須黒清華さんが、不動産のプロ・牧野知弘さんに切り込んだ対談で明かされたのは、「2030年以降、東京の郊外から不動産大暴落が始まる」という、衝撃的な未来予測でした。
この記事では、人気YouTube番組「ReHacQ」で語られた、もはや他人事ではない「新・空き家問題」と、来るべき「大量相続時代」が引き起こす、恐るべきシナリオの全貌を徹底解説します。
これは、遠い未来の話ではありません。あなたの、そしてあなたの家族の資産を守るために、今、知っておかなければならない、不都合な真実の物語です。

動画で紹介された投資術を、初心者でも分かるようにまとめました。
続編:【問題だらけの住宅相続】空き家になる前の早めの対策が吉!売れない・貸せない親の家はどうすべき?【須黒清華】
注意:投資は自己責任でお願いします。この記事は動画の内容をまとめたものであり、投資を推奨するものではありません。
日本全国で深刻化する「空き家問題」の現状
まず、牧野さんが指摘したのは、空き家問題がもはや地方だけの問題ではなく、日本全体を蝕む深刻な社会問題になっているということです。
空き家は「30倍」に増加。止まらない右肩上がりのグラフ
- 衝撃のデータ
- 牧野さんによると、空き家の調査が始まった1960年頃には約30万戸だった空き家が、現在では約900万戸、実に30倍にまで増加しています。
- 唯一の右肩上がりグラフ
- 戦後、一貫して右肩上がりの成長を続けるグラフはなかなかありませんが、空き家の数は「一度も下がることなく、増え続けている」という衝撃的な事実が語られました。
空き家の「内訳」:賃貸用と個人住宅、それぞれの課題
一言で「空き家」と言っても、その内訳には2つの大きな種類があります。
- 賃貸用の空き家(約443万戸)
- 賃貸アパートやマンションの空室、戸建て賃貸などで、全体の約半分を占めます。しかし、この現状にもかかわらず、未だに新しい賃貸物件が次々と建設され続けているという矛盾が指摘されました。東京の特区でも、区によっては賃貸用空き家率が10〜20%に達している場所があると言います。
- 個人の住宅(約385万戸)
- 「実家」がこれに該当します。親が亡くなった後、子どもがすでに自分の家を持っているなどの理由で、すぐに住む人がいない家が空き家になります。
- 「いつか住むかもしれない」という放置
- 多くの人が「いつか住むかもしれない」「思い出があるから売りたくない」といった理由で、空き家をそのまま放置してしまうことが、個人住宅の空き家が増え続ける最大の原因だと指摘されました。
- 「いつか住むかもしれない」という放置
- 「実家」がこれに該当します。親が亡くなった後、子どもがすでに自分の家を持っているなどの理由で、すぐに住む人がいない家が空き家になります。
「東京も例外ではない」驚きの空き家状況
「東京は人口が増えているから大丈夫」という考え方は、もはや過去のものだと牧野さんは警鐘を鳴らします。
- 東京の空き家は「圧倒的1位」の90万戸
- 全国900万戸の空き家のうち、約1割にあたる90万戸が東京に集中しており、その数は全国で圧倒的な1位です。
- 見えにくい「マンションの空き家」
- 東京の空き家の約7割は、戸建てではなく「マンション(共同住宅)」の空き家です。外から見ても住人がいないことが分かりにくいため、私たちが普段意識することはありませんが、実際には多くのマンションで空き室が発生しています。
- 管理費滞納とスラム化のリスク
- 特に問題なのが、相続された古いマンションで、相続人が不明だったり、管理費や修繕積立金を滞納したりするケースです。これが積もり積もると、マンション全体の大規模修繕ができなくなり、最終的には「スラム化」するリスクがあると警告されました。
- スラム化の現実
- ゴミの放置、電気切れ、エレベーターの故障、さらには、管理が行き届かないがゆえに、怪しい外国人などが複数人で住みつき、ルール違反が横行するといった状況に陥る可能性があります。
- スラム化の現実
- 特に問題なのが、相続された古いマンションで、相続人が不明だったり、管理費や修繕積立金を滞納したりするケースです。これが積もり積もると、マンション全体の大規模修繕ができなくなり、最終的には「スラム化」するリスクがあると警告されました。
「大量相続時代」の到来
牧野さんは、日本の人口構成の変化、特に高齢化の進展が、不動産市場に決定的な影響を与えると予測します。
迫り来る「二次相続」の波
- 「後期高齢単独世代」の増加
- 75歳以上の後期高齢者のうち、一人暮らしの「後期高齢単独世代」が過去20年で3倍に増加。彼らが亡くなる「二次相続」の時期が、2030年以降に本格的に到来します。
- 相続対策の遅れ
- 一次相続(夫婦のどちらかが亡くなる)では、配偶者特別控除などで相続税がかからないケースがほとんどです。しかし、二次相続では配偶者控除がなくなり、多額の相続税が発生するケースが激増します。
- 「日本は相続税率の高い国」
- 日本の相続税の最高税率は55%と、世界でも有数の高さです。不動産しか資産がない場合、相続人が税金を払うために、強制的に不動産を売却せざるを得ない状況が大量発生すると予測されます。
- 「日本は相続税率の高い国」
- 一次相続(夫婦のどちらかが亡くなる)では、配偶者特別控除などで相続税がかからないケースがほとんどです。しかし、二次相続では配偶者控除がなくなり、多額の相続税が発生するケースが激増します。
東京の郊外から始まる「不動産大暴落」のシナリオ
- 「大量売却」と「買い手不在」
- 2030年以降、特に都心のブランドエリア以外の、東京の郊外(世田谷、杉並、練馬など)の戸建てやマンションで、大量の相続不動産が市場に出回る一方、人口減少や若者の都心回帰により、買い手が見つからなくなる事態が起こると予測。
- 不動産価格の「二極化」の加速
- 結果として、世田谷の普通の一軒家でも、「運と安くしないと売れない」状況が常態化し、不動産価格の「二極化」がさらに加速すると警告します。一部の超都心物件は維持されるかもしれませんが、多くの地方や郊外の物件は価値が大幅に下落するでしょう。
- 「2040年までには確実」という衝撃予測
- このシナリオは、不老長寿の薬が開発されたり、大量の移民が流入したりしない限り、人口構成のデータから見て「ほぼ確実」に、2040年までには起こると牧野さんは断言します。
「住む家」と「投資物件」の未来
「投資家」と「居住者」の二極化するマーケット
- 投資家マーケット
- 東京の超都心部では、海外の富裕層や投資家による「投資ゲーム」が繰り広げられています。彼らは居住目的ではなく、キャピタルゲイン(転売益)を狙って高額な物件を買い、引き渡し直後に高値で転売を試みています。 しかし、管理費や修繕積立金の概念を知らない外国人投資家がいたり、夜間も電気がついていない「ゴーストマンション」化するリスクも指摘されました。
- 居住者マーケット
- 一方で、本当に住むことを目的としたマーケットは、今後変化すると予測されます。
- 「買いやすくなる未来」
- 将来のZ世代やアルファ世代は、空き家が増えることで、今よりも家を買いやすくなる可能性があると言います。
- 「町を選ぶ」時代へ
- 在宅勤務の普及などにより、通勤時間よりも「自分の家のある町でどう暮らすか」という視点が重要になります。これにより、人気のある街の価値は維持されつつ、そうでない街は価値が下がる「町の二極化」が進みます。
- 「買いやすくなる未来」
- 一方で、本当に住むことを目的としたマーケットは、今後変化すると予測されます。
住宅相続、今からどう備えるべきか?
- 早めの「相続対策」が不可欠
- 親が生きているうちに、相続するかもしれない不動産について話し合い、早めに売却するなどの対策を立てることが重要です。親御さんが認知症になってしまうと意思決定ができなくなり、売却が非常に困難になります。
- 「いらない家」は早めに手放す勇気
- 感情的な思い入れを捨て、資産価値のない家は早めに「負動産」として手放す決断が必要です。
- 不動産の「価値」を正しく見極める
- 「親が〇〇万円で買った家だから、今も同じくらいで売れるはず」という思い込みは危険です。郊外のマンションが数百万単位でしか売れない現実も踏まえ、地方自治体の人口増減データなどを自分で調べて、客観的に価値を判断する目を養うことが大切です。
賃貸用住宅が増え続けている理由
賃貸用の空き家が全国で大量にあるにもかかわらず、なぜ新しい賃貸アパートやマンションが建てられ続けているのか。牧野さんはその理由として「相続税対策」を挙げます。
相続税対策としての賃貸経営
- 土地の評価減
- 何も建っていない「更地」のままだと、土地は路線価などを基にそのまま評価され、高額な相続税がかかります。しかし、その土地にアパートやマンションを建てて人に貸していると、「貸付地」として評価が下がり、相続税を圧縮できるというメリットがあります。
- 借入金の控除
- アパートなどを建てるために銀行からローンを組んだ場合、その借入金の残高部分も相続評価額から差し引くことができるため、さらに相続税を減らす効果があります。
アパート建築会社・不動産会社の営業攻勢
こうした相続税対策のニーズに対し、アパート建設会社や不動産会社は「このままだと多額の相続税がかかりますよ」と、土地を持つオーナー(親世代)に積極的に営業をかけます。
そして「アパートを建てれば税金が安くなり、家賃収入で子どもも楽に暮らせる」といったトークで契約を促すのです。
供給過剰と「負動産」化のリスク
しかし、同じような営業が地域のあちこちで行われるため、結果として同じようなアパートが乱立し、供給過剰に陥ります。
すると、入居者がなかなか見つからず空室が増えたり、家賃を下げざるを得なくなったりして、当初の目論見通りにはいきません。
結局、相続した子どもは、家賃収入が得られないだけでなく、借金だけを相続する「負動産」を抱えることになってしまうリスクを警告しました。
不動産業界の未来と「改革」の必要性
動画の議論全体を通して、日本の不動産市場が抱える構造的な問題と、その改革の必要性についても語られました。
「知識武装」の重要性
不動産取引は情報格差が大きく、消費者が損をしないためには、SNSなどで積極的に情報を集め、「知識武装」することが何よりも重要です。
国や自治体も様々な情報や制度(例:相続土地国庫帰属制度、空き家バンク)を提供していますが、「発表した後は見たもの勝ち」という側面があるため、自ら学ぶ姿勢が求められます。
「空き家バンク」の活用と新しいライフスタイル
全国の空き家情報を集約した「空き家バンク」は、地方への移住や「二拠点・多拠点生活」を希望する人にとっては非常に有用なツールです。
実際に、空き家を安く購入し、DIYでリノベーションして、使わない時は民泊で貸し出すなど、趣味と実益を兼ねた新しいライフスタイルを享受している人々の事例も紹介されました。これにより、空き家問題がポジティブな形で解決される可能性も示唆されています。
「コンパクトシティ化」という行政課題
地方の人口減少が進む中で、行政サービス(福祉、商業など)を維持するためには、住民を一定のエリアに集約させる「コンパクトシティ化」が不可欠です。
これにより、中間地域に点在する空き家は解体され、主要都市やコンテンツが豊かな街に人が集約されていく未来が描かれました。
「外国人による土地購入問題」
水源地や国境に近い土地が外国人に買われている問題は、安全保障上の懸念もあります。
しかし、これは「日本人が買わないから、やむなく売っている」という現実も背景にあると指摘。国として対策を講じる必要性があるとしつつも、日本に住む外国人が370万人を超える中で、彼らとどう共存していくかも重要なテーマであると語られました。
まとめ
今回は、不動産プロデューサー・牧野知弘さんが描く、日本の不動産市場の、少し怖いけれど、データに基づいたリアルな未来について解説しました。
「空き家問題」と「大量相続時代」。この2つの巨大な波が重なる2030年以降、日本の不動産市場が、過去の常識が全く通用しない「大転換期」を迎えることは、もはや避けられないのかもしれません。
最後に、あなたの資産と未来を守るために、この議論から心に刻むべき「3つの教訓」を振り返りましょう。
- 「東京だから安全」という神話は、すでに崩壊している
- 日本で最も空き家が多いのは、東京です。特に、管理が行き届かなくなった古いマンションは、将来「スラム化」するリスクを秘めています。
- あなたの「実家」が、将来「負動産」になるリスクを直視する
- 「大量相続」で、都心以外の郊外の物件は「売りたくても買い手がつかない」時代が到来します。感情的な思い入れはいったん脇に置き、親が元気なうちに、その資産価値を冷静に評価し、家族で話し合うことが不可欠です。
- これからは「家」ではなく「町」を選ぶ時代になる
- 不動産価値の「二極化」が加速します。価値を維持するのは、再開発などで人が集まり続ける、魅力ある「町」の物件だけ。その見極めこそが、資産防衛の鍵となります。
この予測は、私たちを脅かすためのものではありません。未来を正しく知ることで、今から備えることができる、という貴重な“警告”です。この記事が、あなたと、あなたの家族の未来について、真剣に考えるきっかけとなれば幸いです。
本記事は動画の内容をまとめたものであり、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。