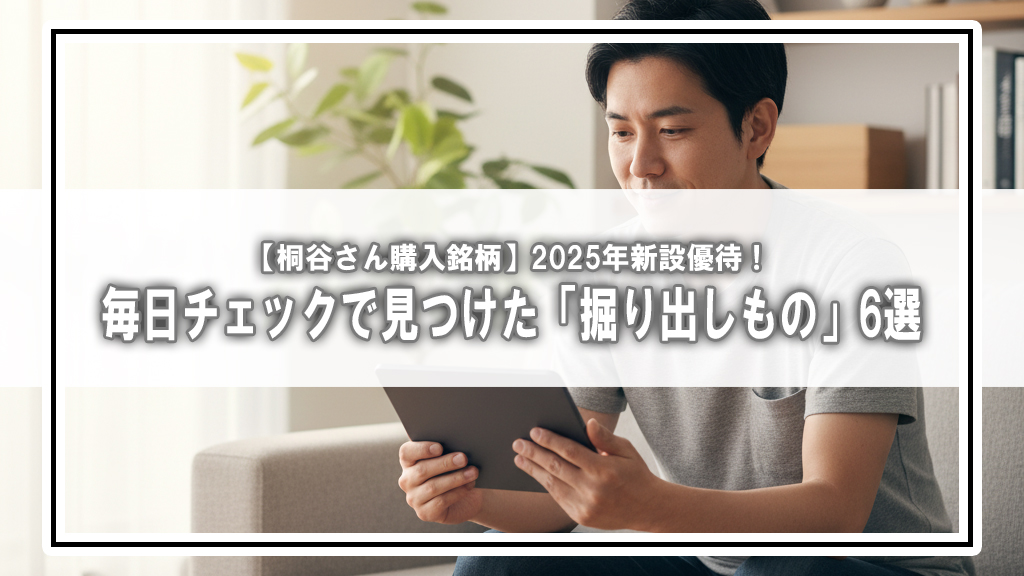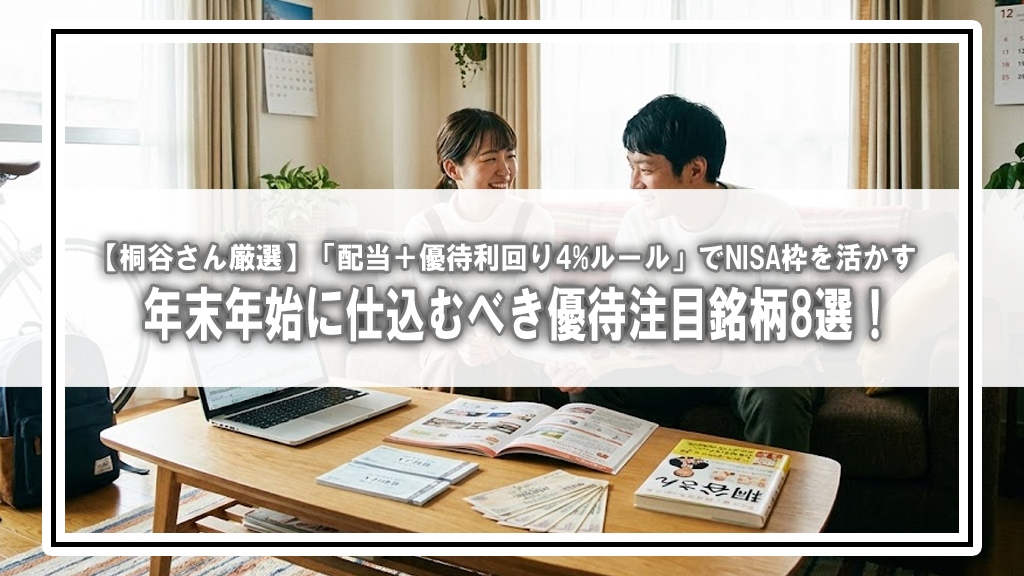【不動産Gメンが暴露】業界最大のタブー「両手取引」の闇と「絶対に買ってはいけない物件」4選【ReHacQ動画まとめ】
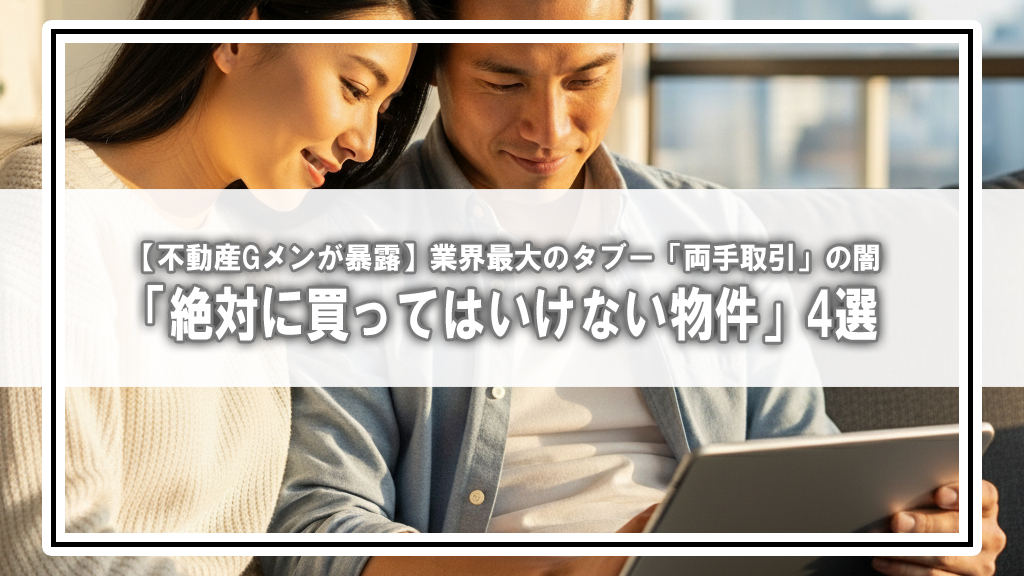
不動産投資──有形資産ならではの安定感、インフレへの強さ。多くの投資家が、ポートフォリオの重要な柱として検討する、魅力的なアセットクラスです。
しかし、そのきらびやかなイメージの裏側で、あなたの資産を静かに蝕む、業界の構造的な“闇”が存在することをご存知でしょうか?
元・大手不動産のトップ営業マン「不動産Gメン」こと滝島一統さんが、人気YouTube番組「ReHacQ」で、そのすべてを暴露しました。
この記事では、彼の衝撃的な内部告発を基に、日本の不動産取引を歪める「両手取引」の実態から、プロが断言する「買った瞬間に負債と化す『負動産』」の具体的な特徴までを徹底解説。
これは、不動産はもちろん、REITや不動産株に投資するすべての人にとって、大切な資産を「落とし穴」から守るための、必読の防衛マニュアルです。
※本記事は動画の内容をまとめたものであり、特定の企業や個人を批判する意図はありません。

動画で紹介された投資術を、初心者でも分かるようにまとめました。
続編:【高橋弘樹vs不動産Gメン滝島】不動産市場の今を徹底解説!掘り出し物件の見つけ方とは?…タワマンは危険!? 地震リスクと不動産市場の真実【ReHacQ】
注意:投資は自己責任でお願いします。この記事は動画の内容をまとめたものであり、投資を推奨するものではありません。
不動産Gメン滝島とは何者か?
まず、滝島さんがなぜ「不動産Gメン」として情報発信を始めたのか、その背景が語られました。
- 元・大手不動産会社のトップ営業マン:
滝島さんは、新卒で入社した大手不動産会社で、入社3年目にして全国トップの営業成績を収めるほどのエリートでした。しかし、その過程で業界の様々な「不都合な真実」を目の当たりにします。 - 情報発信のきっかけは「業界への憤り」:
彼が特に問題視したのが、顧客の利益よりも自社の利益を優先する「両手取引」の横行や、顧客を騙すような営業手法がまかり通っている業界の体質でした。優秀な同僚が、会社の利益追求と顧客への誠実さの板挟みになって辞めていく姿を見て、業界を変えたいという強い思いを抱くようになります。 - YouTubeでの”内部告発”:
退職後、彼は「不動産Gメン」としてYouTubeチャンネルを開設。不動産業界の裏側や、消費者が損をしないための知識を、実名・顔出しで発信し始めました。これは、業界に対する彼の並々ならぬ覚悟の表れと言えます。
業界最大のタブー「両手取引」という”闇”
滝島さんが最も強く批判するのが、日本の不動産業界に蔓延る「両手取引」という仕組みです。
- 「両手取引」とは?
通常、不動産取引では「売主側の仲介会社」と「買主側の仲介会社」がそれぞれ存在します。しかし、「両手取引」では、一つの不動産会社が売主と買主の両方から仲介手数料を受け取ります。 - 何が問題なのか?
- 利益相反: 不動産会社は、売主からは「高く売りたい」、買主からは「安く買いたい」という相反する要望に応えることになります。しかし、手数料を最大化するため、買主よりも売主の利益を優先する構造的な問題が生まれます。
- 情報の囲い込み: 両手取引を狙う不動産会社は、物件情報を他の不動産会社に公開せず、自社だけで抱え込む「囲い込み」を行います。これにより、売主はより良い条件で買ってくれる買主と出会う機会を失い、買主は市場にあるはずの物件情報にアクセスできなくなります。
- 価格の不透明性: 本来であればもっと安く買えたはずの物件を、相場より高く買わされてしまう温床となっています。
- なぜ横行するのか?
両手取引は、アメリカなど多くの国では法律で禁止されていますが、日本では合法です。これが、不動産価格が不透明で、消費者が損をしやすい構造の根源にあると滝島さんは断言します。
- 片手取引(One-sided transaction)
- 不動産会社が「売主」か「買主」どちらか一方のみを仲介する取引。
- 仲介手数料は一方からのみ受け取る。
- 利益は少ないが、公平性が保ちやすい。
- 両手取引(Double-sided transaction)
- 1社の不動産会社が「売主」と「買主」の両方を仲介する取引。
- 仲介手数料を双方から受け取れるので収益性が高い。
- ただし利益相反が起こりやすく、売主・買主どちらの利益を優先するかが問題になることがある。
「絶対に買ってはいけない物件」
動画では、プロの視点から見た「買ってはいけない物件」の具体的な特徴が語られました。
1. 新築ワンルームマンション投資
- なぜ危険か? 「節税になる」「生命保険の代わりになる」といったセールストークで販売されますが、そのほとんどが買った瞬間に価値が2〜3割下落する「負動産」であると断言。業者が多額の利益を乗せているため、市場価格よりはるかに高い値段で買わされているケースがほとんどです。
2. 駅から徒歩15分以上の物件
- なぜ危険か? 将来、売却や賃貸に出す際に、買い手や借り手が見つかりにくく、資産価値が大きく下落するリスクが非常に高いです。特に、人口減少社会に突入する日本では、この傾向はさらに加速すると予測されます。
3. 旧耐震基準のマンション(1981年以前)
- なぜ危険か? 震度6〜7の大地震で倒壊するリスクがあるとされています。また、住宅ローン控除が使えない、ローン審査が通りにくいなど、金銭的なデメリットも非常に大きいです。
4. 違法建築・再建築不可物件
- なぜ危険か? 現在の法律では同じ建物を建て直すことができない土地です。ローンが組めないことが多く、売却も極めて困難。まさに「塩漬け」になってしまう典型的なパターンです。
プロが実践する「掘り出し物件」の見つけ方
滝島さんは、「掘り出し物」とは単に価格が安い物件ではなく、「本来の価値よりも安く売られている物件」だと定義します。そして、そうした物件を見つけるための具体的な3つのステップを伝授しました。
Step 1:「相場観」を徹底的に養う
- どうやって?
- SUUMOやHOME’Sといったポータルサイトで、自分が興味のあるエリア(駅)の物件情報を最低でも3ヶ月間、毎日見続けることが全ての基本だと滝島さんは語ります。
- 見るべきポイント:
- 新着物件は何か?
- 価格が変更された物件はどれか?(値下げ・値上げ)
- 成約して消えた物件はどれか?
- なぜ重要か?
- これを続けることで、「このエリアでこの広さなら、大体〇〇万円くらい」という肌感覚(相場観)が養われます。この相場観がなければ、目の前に掘り出し物が出てきても、それが「安い」と気づくことすらできません。
Step 2:「売り出し価格」と「成約価格」のギャップを知る
- どうやって?
- ポータルサイトに掲載されているのは、あくまで売主の希望である「売り出し価格」です。実際にいくらで売れたかという「成約価格」は、「レインズ・マーケット・インフォメーション」や「土地総合情報システム」といったサイトで誰でも無料で確認できます。
- なぜ重要か?
- この2つの価格を比較することで、「このエリアでは大体〇%くらい値引き交渉に応じてくれる可能性がある」というリアルな取引価格が見えてきます。
Step 3:「優良な仲介担当者」を味方につける
- どうやって?
- 信頼できる担当者を見つけたら、「私は本気で探しています」という姿勢を見せ、具体的に希望条件を伝えます。
- 良い関係を築くことで、担当者はポータルサイトに掲載される前の「未公開情報」を優先的に紹介してくれるようになります。
- なぜ重要か?
- 本当の掘り出し物件は、情報が公開される前に水面下で売れてしまうことがほとんどです。プロのネットワークをいかに活用できるかが、勝負の分かれ目となります。
タワーマンションは本当に”危険”なのか?
多くの人が憧れるタワーマンション。しかし、その裏に潜むリスクについても、滝島さんは警鐘を鳴らします。
タワマンの2大リスク
- 修繕積立金の”破綻”リスク:
- 問題点: タワーマンションは、エレベーターや外壁などの大規模修繕に莫大な費用がかかります。しかし、新築時に販売価格を安く見せるため、当初の修繕積立金が意図的に低く設定されているケースがほとんどです。
- 将来どうなる? 10〜15年後の大規模修繕の際に資金が足りず、修繕積立金が当初の5倍、10倍に跳ね上がる可能性があります。これを払えない住民が増えると、修繕ができずにスラム化したり、管理組合が破綻したりするリスクがあります。
- 管理費・修繕積立金が”家賃化”するリスク:
- 問題点: 上記の理由で高騰した管理費と修繕積立金は、住宅ローンを完済した後も一生涯払い続ける必要があります。月々の支払いが10万円を超えるケースも珍しくなく、これが老後の生活を圧迫する「負の遺産」と化す可能性があります。
滝島さんの結論
タワーマンションを否定はしないものの、購入する際は「長期修繕計画」を必ずチェックし、将来の積立金の値上がり幅が現実的かどうかを厳しく見極める必要がある、というのが滝島さんの見解です。
金利上昇と地震リスク、今後の不動産市場は?
金利上昇の影響
- 短期的には「大きな影響はない」:
現在の日銀の金融政策では、変動金利が急激に上がる可能性は低いと滝島さんは分析します。多くの人が変動金利でローンを組んでいるため、急激な利上げは国民生活を直撃し、政権へのダメージも大きいからです。 - 長期的には「緩やかに上昇」:
ただし、超低金利時代が永遠に続くわけではなく、長期的には緩やかに金利が上昇していく可能性は十分にあります。
地震リスクと不動産価格
- 「喉元過ぎれば熱さを忘れる」:
能登半島地震の後も、都心などの不動産価格に大きな下落は見られませんでした。滝島さんは、人間は大きな災害があっても、時間と共にその記憶が薄れ、不動産価格への影響は限定的になることが多いと指摘します。 - 本当に重要なのは「地盤」:
ただし、個別の物件選びにおいては、ハザードマップを確認し、液状化や浸水のリスクが低い、地盤の強固なエリアを選ぶことが、自身の生命と資産を守る上で極めて重要だと強調しました。
不動産Gメンの教えから学ぶ、3つの教訓
「リート(不動産投資信託)って、なんだか安定してそうだし、始めてみようかな?」
「不動産関連の株って、これからどうなるんだろう?」
そう考えている株初心者の方にこそ、知っておいてほしいことがあります。不動産の世界は、一見すると安定しているように見えて、実は一般の消費者や投資家が知らない「落とし穴」がたくさん潜んでいます。
不動産業界の裏側を知り尽くした「不動産Gメン」滝島さんの言葉は、不動産そのものを買う人だけでなく、リートや不動産関連株に投資する私たちにとっても、非常に重要な道しるべとなります。
1. 「情報の非対称性」を知り、プロの言葉を鵜呑みにしない
滝島さんは、不動産業界に「両手取引」や「情報の囲い込み」といった、業者側に有利な仕組み(情報の非対称性)が蔓延していると警鐘を鳴らしています。これは、株の世界にも通じる非常に重要な教訓です。
証券会社のアナリストレポートや、経済ニュースで「買い推奨」とされているリートや不動産株があったとしても、それを鵜呑みにしてはいけません。 なぜなら、その情報の裏側には、レポートを書いたアナリストや証券会社の何らかの意図(ポジション・トーク)が隠れている可能性があるからです。「この情報は、誰にとって有利な情報なのか?」と一歩引いて考える冷静な視点を持ちましょう。
2. 資産のリスクを見抜くための視点を知る
滝島さんが挙げる「買ってはいけない物件」には、株初心者が避けるべき「買ってはいけない株」との共通点が数多くあります。
1. 割高な資産(買った瞬間に価値が下がるリスク)
- 不動産の例:新築ワンルームマンション
- 解説:業者の利益が多く上乗せされており、市場の適正価格よりも大幅に割高な場合が多い。購入した直後に、市場価格に合わせて価値が大きく下落するリスクがあります。
- 株式の例:人気沸騰中のIPO(新規公開株)
- 解説:上場直後は投資家の期待で価格が高騰しがちです。その熱狂が冷めた後に購入すると、「高値掴み」となり、株価が落ち着く過程で損失を被るリスクがあります。
2. 将来性のない資産(需要が減少していくリスク)
- 不動産の例:駅から遠い物件
- 解説:人口減少が進む日本では、交通の便が悪い物件は将来的に借り手や買い手が見つかりにくくなり、資産価値が大きく下落していく可能性が高いです。
- 株式の例:斜陽産業の株
- 解説:今は配当が高くても、長期的に市場が縮小していく業界(例:ペーパーレス化が進む中の製紙業の一部など)の企業は、将来的に業績が悪化し、減配や株価下落につながるリスクがあります。
3. 脆弱な資産(外的ショックで価値が毀損するリスク)
- 不動産の例:旧耐震基準のマンション
- 解説:大きな地震によって倒壊する物理的なリスクを抱えています。また、ローンが付きにくいなど、金銭的なデメリットも大きいです。
- 株式の例:財務状況が悪い株(自己資本比率が低いなど)
- 解説:借金が多く、自己資本が少ない企業は、不況や金融危機といった外部からの衝撃に耐えられず、倒産してしまうリスクが高い状態です。
4. 流動性の低い資産(売りたい時に売れないリスク)
- 不動産の例:再建築不可物件
- 解説:法的な制約から買い手が極端に限られるため、いざ売却したいと思っても買い手が見つからず、現金化できない「塩漬け」状態になるリスクが非常に高いです。
- 株式の例:出来高が極端に少ない株
- 解説:日々の取引量が少ないため、まとまった株数を売ろうとすると、買い注文がなく、希望する価格で売れない、あるいは全く売れないというリスクがあります。
リートや不動産株に投資する際は、その投資対象が「将来も需要が見込める(好立地など)」「災害に強い」「流動性(売りやすさ)が高い」といった条件を満たしているか、目論見書や財務諸表をしっかり確認する癖をつけましょう。
3. 「相場観」を磨き、自分なりの「割安」の基準を持つ
滝島さんは、「掘り出し物件」を見つけるためには、まず自分自身で「相場観」を養うことが全ての基本だと語ります。これは、株式投資で成功するための最も重要なスキルの一つです。
気になるリートや不動産株を見つけたら、すぐに飛びつくのではなく、最低でも3ヶ月はその値動きを追いかけてみましょう。そして、同業他社の株価や、業界全体のニュースと比較することで、「今の株価は、過去と比べて、また同業他社と比べて割安なのか?」という自分なりの基準(相場観)を養うことができます。この地道な努力こそが、高値掴みを避け、絶好の買い場を見つけるための最強の武器となるのです。
まとめ
今回は、「不動産Gメン」滝島一統さんが暴露した、不動産業界の裏側と、投資家が身を守るための鉄則をご紹介しました。彼の言葉は、不動産というアセットクラスに潜む「情報の非対称性」という、株式投資家にとっても他人事ではないリスクを浮き彫りにします。
あなたが不動産関連の投資で失敗しないために、Gメンが授けた「3つの教訓」を、もう一度心に刻んでください。
- 業界の構造的な“闇”を知り、プロの言葉を鵜呑みにしない
- 仲介会社の利益相反(両手取引)や情報の囲い込みは、投資家のリターンを損なう元凶です。アナリストレポートや営業トークの裏側を常に意識する癖をつけましょう。
- 「買ってはいけない負動産」の類型を、株式投資にも応用する
- 「割高(新築ワンルーム)」「将来性なし(駅から遠い)」「脆弱(旧耐震)」「低流動性(再建築不可)」。この4つの視点は、避けるべき「ダメな株」を見抜く上でも、全く同じように機能します。
- 他人に頼るな。自らの足で、投資対象の「相場観」を磨け
- 毎日ポータルサイトを見続ける。成約価格を調べる。この地道な努力で養われたあなた自身の「相場観」こそが、割高な資産を避け、真に価値のある投資対象を見つけ出す、唯一無二の武器となります。
不動産も株式も、本質は情報戦です。Gメンが授けてくれたこの知識で武装し、見えないリスクからあなたの資産を守り抜き、賢明な投資判断を下してください。
※本記事は動画の内容をまとめたものであり、特定の企業や個人を批判する意図はありません。
本記事は動画の内容をまとめたものであり、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。