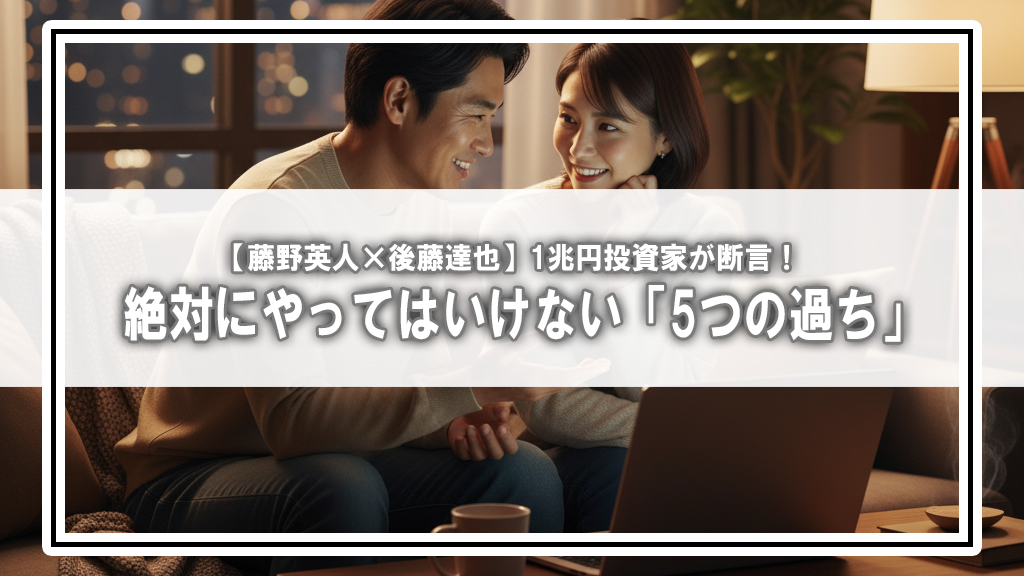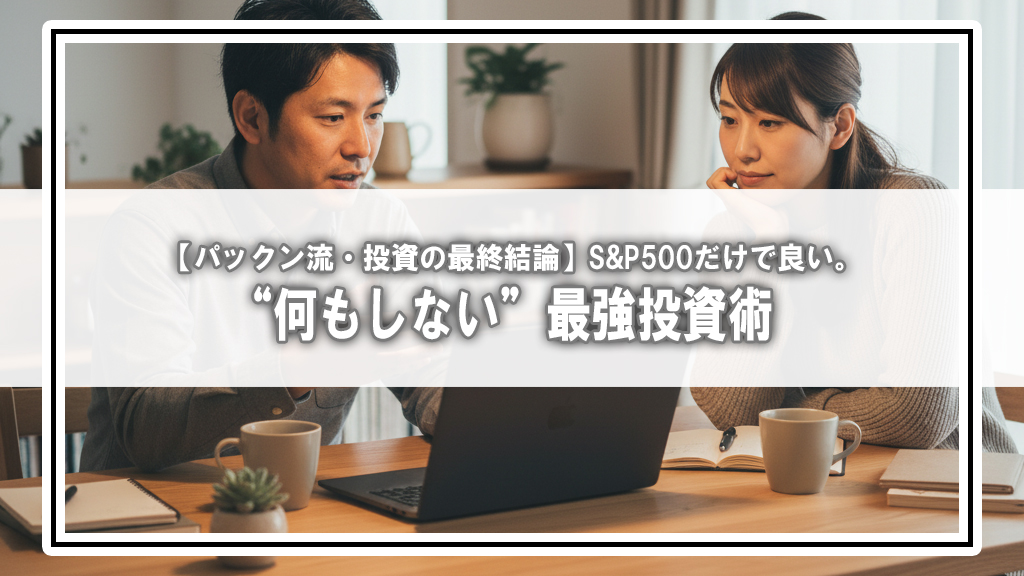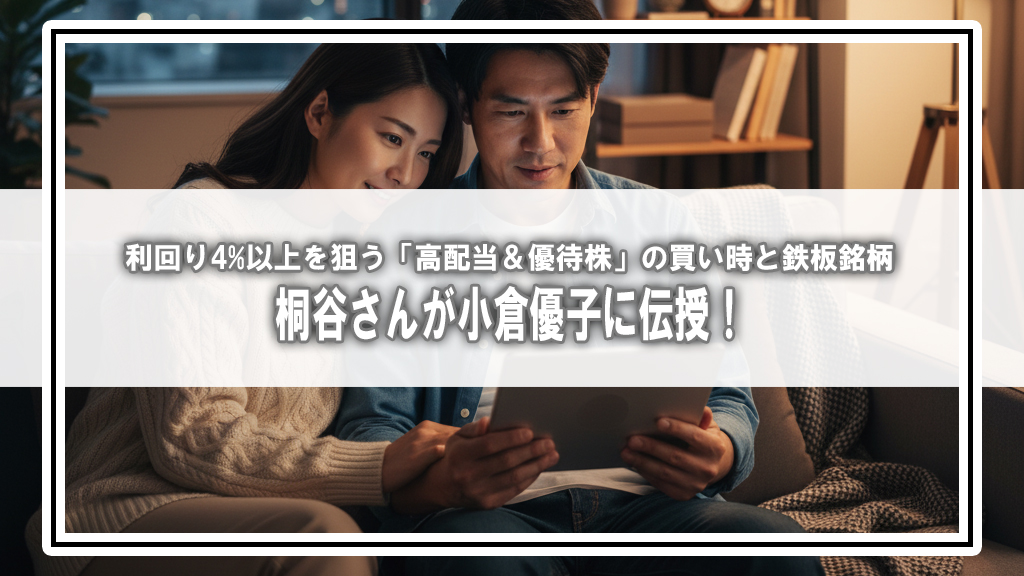【ひろゆき流・人生の最適解】「家は買うな」「結婚は合理的じゃない」論破王が語る、お金と時間の使い方【ReHacQ動画まとめ】

「家は買うべき?賃貸のまま?」「結婚って本当にした方がいいの?」 多くの人が、社会の“当たり前”と自分自身の幸福の間で揺れ動く、人生の重大な選択。
もし、その悩みを、感情論や同調圧力を一切排除し、「究極の合理性」だけで判断したら、どんな答えが導き出されるのでしょうか?
この記事では、日本一の“論破王”ひろゆきさんが、ReHacQの高橋弘樹さんを相手に、家・結婚・仕事・幸福といった人生のあらゆるテーマを「最適化」する、驚くべき思考法を語った対談を徹底解説します。
なぜ彼は「日本の家は買うな」と断言するのか?幸福の本質は「基準値を下げる」ことだと喝破する真意とは?
あなたの“常識”が、今日、覆されるかもしれません。

動画で紹介された内容を、投資初心者でも分かるようにまとめました。
注意:投資は自己責任でお願いします。この記事は動画の内容をまとめたものであり、投資を推奨するものではありません。
お金がなくても豊かに生きる「豊かな貧乏人」という思考法
「お金持ちにならなければ、幸せにはなれないのか?」
物価が高騰し、実質賃金が下がり続ける現代日本で、多くの人が抱えるこの根源的な問い。
この問いに対し、ひろゆきさんが、自身の新著『金持ち 豊かな貧乏人』をテーマに、「お金をかけずに豊かに生きる」ための具体的な思考法と実践術を語りました。
「お金がないと幸せになれない」という”呪い”からの脱却
なぜ、私たちは「お金=幸せ」だと思い込んでしまうのか?
ひろゆきさんは、現代社会、特に日本が「お金がないと不幸である」という強いプレッシャーに満ちていると指摘します。メディアや広告は、高価な商品やサービスを所有することが「豊かな生活」であるかのように描き、私たちは無意識のうちにその価値観を刷り込まれています。
しかし、現実はどうでしょうか。 物価は上がり続け、4世帯に1人が貯蓄ゼロ。多くの人が「金持ち」になることが極めて困難な時代に、この価値観を持ち続けることは、自分自身を追い詰めるだけの“呪い”に他ならない、とひろゆきさんは断言します。
「豊かな貧乏人」という新しいゴール
そこで彼が提案するのが、「豊かな貧乏人」という新しい生き方の指標です。 これは、お金をたくさん持つことを目指すのではなく、「お金を使わなくても、自分の心が豊かになる状態」をゴールに設定する、という発想の転換です。
生活コストを劇的に下げる、ひろゆき流「人間関係の断捨離」
では、「豊かな貧乏人」になるためには、具体的にどうすればいいのか。その第一歩は、生活コスト、特に「人間関係コスト」を徹底的に見直すことだと、ひろゆきさんは語ります。
- 「嫌われる勇気」を持つ:
多くの人が、職場の飲み会や冠婚葬祭、年賀状のやり取りなど、「人から嫌われたくない」という思いから、本当は気乗りしない付き合いにお金と時間を費やしています。 - 合理的に断る:
ひろゆきさんは、「誘われた飲み会に毎回参加しなくても、仕事で結果を出していれば評価は変わらない」「年賀状をやめても、本当に大切な人との関係は途切れない」と主張。他人の評価を気にしすぎず、自分にとって不要な付き合いを合理的に断っていくことが、生活コストを劇的に下げる上で最も効果的だと語ります。
人生の満足度を高める「お金のかからない趣味」のススメ
生活コストを下げて生まれた「お金」と「時間」。それを何に使うべきか。 ひろゆきさんの答えは、「お金のかからない趣味」に再投資することです。
なぜ「お金のかからない趣味」が重要なのか?
- 幸福度の持続性:
- 高価なブランド品を買ったり、高級レストランで食事をしたりする幸福は、瞬間的ですぐに薄れてしまいます。しかし、趣味に没頭する時間は、持続的な満足感や達成感を与えてくれます。
- お金への依存からの脱却:
- 収入が減ったり、仕事を失ったりしても、お金をかけずに楽しめる趣味があれば、精神的な安定を保つことができます。これは、将来への不安を軽減する、強力なセーフティネットになります。
ひろゆきさんが挙げる具体例
- 釣り: 道具にこだわらなければ、初期投資は少なく、自然の中で過ごす時間はプライスレスです。
- 家庭菜園: ベランダのプランターから始められ、自分で育てた野菜を食べる喜びは格別です。
- 楽器演奏: 中古の楽器なら安価に手に入り、一生楽しめるスキルが身につきます。
- 俳句や短歌: 紙とペンさえあれば始められ、日常の風景が全く違って見えてくるようになります。
自分だけの「豊かさの物差し」を見つけよう
このトピックスを通じてひろゆきさんが伝えているのは、社会が押し付ける「豊かさ」の基準に、あなたの幸せを委ねてはいけない、ということです。
自分にとって、何が心地よく、何が楽しいのか。 その「自分だけの物差し」を見つけ、その基準に従って、お金と時間を最適化していく。
それこそが、物価高騰や先行き不透明な時代を、心豊かに生き抜くための最強のスキルなのかもしれません。
家は買うな!賃貸が最強である”不都合な真実”とは?
「いつかは自分の家を持ちたい」 多くの日本人にとって、マイホームの購入は人生の大きな夢であり、目標です。
しかし、ひろゆきさんはこの「常識」に真っ向から異議を唱え、「経済的な合理性で考えるなら、ほとんどの日本人は家を買わない方が得だ」と断言します。
多くの日本人にとって、家は「負債」である
なぜ、家を買うと損をするのか?
ひろゆきさんが「家を買うべきではない」と主張する最大の理由は、日本の人口減少にあります。
- 地価下落という避けられない未来:
都心の一部例外を除き、日本のほとんどの地域では、人口が減るにつれて土地の需要も減り、地価は長期的に下落していきます。 つまり、3,000万円で買った家が、30年後には1,000万円の価値しかなくなっている、ということが当たり前に起こるのです。ローンを払い終えた頃には、資産価値が大きく目減りしている。「資産」のつもりで買った家が、実質的な「負債」と化してしまうリスクが非常に高いと、ひろゆきさんは警鐘を鳴らします。
生涯コストでも「賃貸」が有利
「家賃を払い続けるのはもったいない」という意見に対し、ひろゆきさんは生涯のトータルコストで反論します。
- 持ち家にかかる「見えないコスト」: 持ち家には、住宅ローンの返済以外にも、
- 固定資産税
- 火災保険・地震保険
- 修繕費(外壁塗装、水回りなど)
- マンションの場合は管理費・修繕積立金 といったコストが、所有している限り一生涯かかり続けます。
- 結論:
同じクオリティの物件に住むと仮定した場合、これらの「見えないコスト」を考慮すると、生涯で支払う総額は賃貸の方が安くなるケースが多い、というのがひろゆきさんの分析です。
賃貸がもたらす最強の資産=「流動性(身軽さ)」
ひろゆきさんが賃貸を推す理由は、金銭的なメリットだけではありません。彼は、「いつでも、どこにでも住む場所を変えられる自由」、すなわち「流動性」こそが、変化の激しい現代を生き抜くための最強の資産だと考えています。
- ライフステージの変化に柔軟に対応:
結婚、出産、子どもの独立、親の介護など、人生には様々な変化が訪れます。賃貸であれば、その時々の家族構成や収入に合わせた最適な家に、気軽に住み替えることができます。 - 転職・キャリアチェンジの自由:
「家を買ってしまったから、この土地を離れられない…」 住宅ローンは、時にキャリアの選択肢を狭める“重り”になります。賃貸であれば、より良い仕事を求めて国内外どこへでも移住するという、大胆なキャリアチェンジも可能です。 - 定年後の選択肢が広がる:
定年後、子どもが独立した夫婦二人にとって、都心の広い家は必要ないかもしれません。賃貸であれば、物価の安い地方に移住したり、海外でのんびり暮らしたりと、老後の選択肢が無限に広がります。
それでも「家を買いたい」人へ
ひろゆきさんは、持ち家を完全に否定しているわけではありません。以下のような特定のケースでは、購入を検討する価値があるとも語っています。
- 都心の一等地など、将来的な値上がりが確実に見込める場所
- 「どうしてもこの家に住みたい」という、趣味や嗜好を貫きたい場合
- 経済的な合理性よりも、「自分の城を持つ」という精神的な満足感を優先したい場合
ただし、これらのケースに当てはまらない大多数の日本人にとっては、賃貸の方が合理的である、というのが彼の揺るぎない結論です。
「所有」の時代から「利用」の時代へ
ひろゆきさんの「家は買うな」という主張は、「マイホーム=幸せの象徴」という、私たちが長年抱いてきた価値観を根底から揺さぶります。
しかし、その根底にあるのは、変化の激しい時代を、より自由に、より豊かに生き抜くための、極めて合理的で現代的な生存戦略です。
「所有」することで得られる安心感よりも、「利用」することで得られる「自由」と「身軽さ」に価値を見出す。 家を買う前に、一度立ち止まって、ひろゆきさんの視点から自分のライフプランを見つめ直してみてはいかがでしょうか。
東京の不動産は”異常”である。価格高騰の裏側と、庶民が家を買えない本当の理由
「東京のマンション、高すぎて買えない…」
多くの人が肌で感じるこの悲鳴。しかし、なぜ東京の不動産価格だけが、これほどまでに高騰を続けるのでしょうか?
ひろゆきさんは、この異常な状況の裏側には、もはや日本の一般庶民では太刀打ちできない「国際金融資本の論理」が存在すると指摘します。
東京の不動産は、もはや「日本人のためのもの」ではない
なぜ、東京のマンション価格は高騰し続けるのか?
ひろゆきさんが挙げる最大の理由は、海外の富裕層や投資家による「投資マネー」の流入です。
- 円安が拍車をかける:
歴史的な円安により、海外の投資家から見れば、日本の不動産は「世界の大都市の中で、驚くほど割安」に見えます。例えば、1億円のマンションも、彼らにとっては半額の50万ドル程度で買える感覚なのです。 - 目的は「キャピタルゲイン(転売益)」:
彼らの多くは、東京に住むためにマンションを買っているのではありません。数年後に価格が上がったタイミングで転売し、その差額で利益を得る「キャピタルゲイン」が目的です。東京の不動産は、もはや居住用ではなく、金融商品の一つのように扱われているのです。
香港の事例に学ぶ「不動産価格の未来」
ひろゆきさんは、この現象を香港の状況と重ね合わせます。 香港では、世界中の富裕層が不動産を買い漁った結果、価格が異常に高騰。医師や弁護士といった高給取りでさえ家を買うことができず、一般市民は狭い住居に追いやられるという深刻な社会問題が発生しました。
東京も、このままでは香港と同じ道を辿り、「住む場所としての東京」と「投資対象としての東京」が完全に乖離していくと、ひろゆきさんは警鐘を鳴らします。
なぜ政府は「何もしない」のか?
では、なぜ政府は、この異常な不動産高騰に対して有効な手を打たないのでしょうか。ひろゆきさんは、その背景にある「政治的な思惑」を指摘します。
- 地価対策は「票にならない」:
不動産価格が下がると、すでに家を所有している富裕層や高齢者層の資産価値が目減りします。彼らは選挙における重要な票田であるため、政府としては地価を下げるような政策は打ちにくいのです。 - 固定資産税という「うまみ」:
不動産価格が上がれば、国や自治体に入ってくる固定資産税の税収も増えます。 政府にとっても、不動産価格が高いことのメリットは大きいのです。
シンガポールという「成功事例」
一方で、ひろゆきさんは有効な対策を打っている国の例としてシンガポールを挙げます。
- HDB(住宅開発庁)という仕組み:
シンガポールでは、政府系の機関であるHDBが、国民向けに安価で質の高いマンションを大量に供給しています。国民の約8割がこのHDBに住んでおり、これにより、海外からの投資マネーで市場価格が高騰しても、国民の住環境は守られています。 - 日本の「やればできるのに、やらない」現実:
ひろゆきさんは、日本もやろうと思えばシンガポールのような政策は可能だとしつつも、前述の政治的な理由から「やらないことを選んでいる」と、政府の姿勢を厳しく批判しています。
「東京で家を買う」という夢の終わり
このトピックスから見えてくるのは、東京で家を買うという行為が、もはや個人の努力や年収だけではどうにもならない、世界的なマネーゲームに巻き込まれているという厳しい現実です。
ひろゆきさんの言葉は、私たちに「東京で無理して家を買う」という、かつての“常識”や“夢”を一度リセットし、もっと地方に目を向けたり、賃貸で身軽に生きたりと、自分なりの幸福な住まい方を再定義する必要があることを教えてくれます。
東京の不動産市場の現状を冷静に理解し、その上で自分にとって最適な選択は何かを考える。そのための非常に重要な視点が、この対談には詰まっています。
【結婚・子育て論】コスパ最悪はウソ?幸福度を高める”合理的”な選択とは
「結婚はコスパが悪い」
「子どもを持つと、自分の時間がなくなる」
現代社会では、結婚や子育てに対して、こうしたネガティブなイメージが語られがちです。しかし、ひろゆきさんは統計データや研究結果を基に、それらのイメージとは全く異なる「結婚と子育てのポジティブな側面」を、極めて合理的に解説しています。
子育てが「人生の満足度」を劇的に高めるという事実
なぜ、子どもを持つと幸福度が上がるのか?
ひろゆきさんは、「子どもを持つ親は、持たない人に比べて、人生の終盤における満足度が非常に高い」という研究結果を紹介します。
- 短期的な大変さと、長期的な幸福:
子育ては、お金も時間もかかり、短期的には大変なことの連続です。しかし、子どもが成長し、家族としての思い出が積み重なっていく過程で得られる幸福感は、何物にも代えがたい大きなものである、とデータは示しています。 - 「自分のため」から「誰かのため」へ:
子育てを通じて、親は「自分のため」だけでなく、「この子の未来のために」という新しい生きがいを見出します。この「利他的」な視点が、人生に深みと満足感を与えるのではないか、とひろゆきさんは分析します。
地方での子育てという選択肢
さらに、ひろゆきさんは地方で子育てをするメリットを強調します。 都会の狭い家で高い生活費に苦しむよりも、地方で広く、安価な家に住み、豊かな自然の中で子どもを育てる方が、親にとっても子どもにとっても、より幸福度が高い生活を送れる可能性を指摘しました。
結婚は「健康」と「寿命」への最高の投資
「おひとりさま」という生き方が尊重される一方で、ひろゆきさんは結婚がもたらす心身の健康へのメリットをデータで示します。
- ストレス軽減と寿命の延長:
統計的に、結婚している人は独身者に比べてストレスレベルが低く、平均寿命が長いという傾向があります。 - なぜ健康になるのか?
安定したパートナーがいることで、精神的な安らぎが得られるだけでなく、食生活が改善されたり、病気の際に看病してもらえたりと、日々の生活におけるセーフティネットとして機能するためだと考えられます。ひろゆきさんは、これを「健康保険のようなもの」と表現し、結婚の合理的なメリットとして解説しました。
離婚制度という「縛り」が、関係を強くするという逆説
「簡単に離婚できないから、結婚はリスクが高い」と考える人もいます。しかし、ひろゆきさんは、この「縛り」にこそ、長期的な人間関係を維持するための重要な機能があると、ユニークな視点を展開します。
- 「続けるための努力」を生む制約:
もし何の制約もなく、いつでも簡単に関係を解消できるとしたら、多くのカップルは些細なすれ違いや喧嘩で別れてしまうかもしれません。 - 「縛り」があるからこそ:
離婚というハードルがあるからこそ、夫婦は問題を乗り越え、関係を修復するためのコミュニケーションや努力をします。このプロセスを通じて、絆がより深まっていく側面があるのではないか、というのがひろゆきさんの分析です。
「非合理」の中にある、人生の豊かさ
ひろゆきさんの結婚・子育て論は、一見すると非常にドライで合理的に聞こえます。しかし、その根底にあるのは、人生の豊かさとは、金銭的なコストパフォーマンスだけでは測れない、「非合理」な領域にこそ存在するという、温かいメッセージです。
お金や時間の「コスト」の先に、それを上回る精神的な「リターン(幸福感、満足度)」がある。 結婚や子育てについて考えるとき、この長期的な視点を持つことが、より後悔のない選択をするための鍵となるのかもしれません。
信じる者は救われる?”良い宗教”と”危険な宗教”の見分け方
「宗教」と聞くと、少し怪しい、あるいは自分には関係ないと感じる人も多いかもしれません。しかし、ひろゆきさんは「幸福度」という観点から、宗教が人生に与える影響を非常に興味深く、かつ合理的に分析しています。
信仰と幸福度の驚くべき関係
「信じている人の方が、死ぬ時に幸せ」というデータ
ひろゆきさんは、「信仰心がある人の方が、死を迎える瞬間に『自分の人生は幸せだった』と感じる割合が高い」という研究結果を紹介します。
これは、特定の宗教の教えが優れているという話ではありません。 人生には、科学や合理性だけでは説明できない「死」や「不運」「理不尽」が必ず訪れます。そうした時に、「死んだら天国に行ける」「これは神が与えた試rlenだ」といった物語(ストーリー)を信じることができると、人は心の平穏を保ちやすく、困難な状況を受け入れやすくなる、とひろゆきさんは分析します。
つまり、信仰とは、人生という不確実なものと向き合うための、強力な精神的なセーフティネットとして機能しているのです。
ひろゆき流「良い宗教」と「危険な宗教」の見分け方
では、数ある宗教の中から、どうすれば「安全な」宗教を見分けることができるのでしょうか。ひろゆきさんは、カルトなどに騙されないための、非常にシンプルで実用的な2つの基準を提示します。
基準1:お金儲けが主目的になっていないか?
- 危険な宗教の特徴:
お布施や献金の額をやたらと気にしたり、高額な商品を売りつけたりするなど、信者からお金を集めることが活動の中心になっている宗教は非常に危険です。 - 良い宗教の傾向:
伝統的な仏教やキリスト教なども、もちろん運営のためにお金は必要としますが、それが主目的ではありません。あくまで教えを広めることや、コミュニティを維持することが中心です。
基準2:教祖が死んでから「3代」以上続いているか?
- 危険な宗教の特徴:
教祖が存命中の宗教や、亡くなってからまだ代替わりが少ない宗教は、教祖の個人的な欲望やカリスマによって組織が動いている可能性が高いです。そのため、教義がコロコロ変わったり、信者が教祖の私利私欲のために利用されたりするリスクがあります。 - 良い宗教の傾向:
ひろゆきさんは、「教祖が死んで3代以上続いている」ことを一つの目安として挙げています。代替わりを重ね、長い歴史の中で多くの人々に受け入れられ続けてきた宗教は、教義や組織が普遍的なものへと洗練されており、比較的安全性が高いと言えます。
私たち日本人が無意識に信じる「日本教」の正体
「自分は無宗教だ」と思っている日本人。しかし、ひろゆきさんは「そんなことはない。ほとんどの日本人は『日本教』という宗教を信じている」とユニークな視点を展開します。
「日本教」の教義とは?
- 勤勉・正直・清潔:
「真面目に働くことは美しい」「嘘をつくのは悪いことだ」「お風呂に入って体を清潔に保つべきだ」…これらは、私たちが子どもの頃から親や学校に教え込まれ、何の疑いもなく信じている価値観です。 - 他の宗教との比較:
しかし、ひろゆきさんは「海外に行けば、働かずに暮らすのが上手い人、息を吐くように嘘をつく文化、毎日シャワーを浴びない人々はたくさんいる」と指摘します。 - 結論:
つまり、「勤勉・正直・清潔」は、世界共通の普遍的な価値観ではなく、日本という国・社会が共有している、一種の宗教的な価値観(=日本教)なのではないか、と分析するのです。
この「日本教」の存在を自覚することで、私たちは自分たちの常識を客観視し、より多様な価値観を受け入れるきっかけを得ることができるのかもしれません。
日本の未来は暗い?ブロック経済化する世界で、私たちが生き残る道
「日本の景気、これからどうなるの?」 「世界情勢が不安定だけど、私たちの生活や投資にどう影響するの?」
そんな漠然とした未来への不安に対し、ひろゆきさんが極めてドライかつ現実的な視点で、これからの世界と日本の姿を語りました。
投資の”常識”が変わる時代の到来
トランプ政権以降の変化
ひろゆきさんは、トランプ前米大統領の登場が、世界の大きな転換点になったと指摘します。 それまでの「グローバル経済(世界が一つになって、自由に貿易する)」という流れが終わりを告げ、「自国の利益を最優先する」という考え方が世界の主流になりました。
- 投資環境への影響:
これにより、かつてのように「アメリカのインデックスファンド(S&P500など)を買っておけば安泰」という、シンプルな投資の“正解”が通用しにくくなっていると、ひろゆきさんは分析します。いつ、どの国が、どんな政策を打ち出してくるか予測が難しくなり、投資の難易度は上がっているのです。
世界は「ブロック経済化」へ。そのリスクとは?
「自国第一主義」が招く未来
アメリカの「アメリカ・ファースト」に始まり、世界中で「自国さえ良ければいい」という、内向きな考え方(ナショナリズム)が強まっています。ひろゆきさんは、その象徴的な事例として「ブレグジット(イギリスのEU離脱)」を挙げます。
- ブレグジットの“失敗”:
イギリスは、移民問題などを理由にEUを離脱しましたが、結果として経済は悪化し、物価は高騰。多くの国民が「離脱は間違いだった」と感じています。 - ブロック経済化のリスク:
このように、各国が自国の利益だけを追求し、関税などで他の国を排除する「ブロック経済化」が進むと、自由な貿易が阻害され、結果的に世界全体の経済が停滞・悪化するリスクが高まります。
日本の労働者が直面する「厳しい現実」
グローバル化が進んだ結果、日本の労働者は、これまでとは全く異なる競争に晒されていると、ひろゆきさんは指摘します。
発展途上国の台頭という脅威
- 仕事と給料が奪われる:
インターネットの普及により、かつては日本国内で行われていたプログラミングやデザイン、データ入力といった仕事が、より人件費の安いインドや東南アジアの優秀な人材に奪われていく流れは、もはや止められません。 - 日本の「平均的な労働者」の未来:
これにより、日本の「平均的なスキル」しか持たない労働者の給料は、上昇するどころか、発展途上国の水準に引きずられて下がっていく可能性があると、ひろゆきさんは厳しい未来を予測します。
国や会社に依存せず、「個人」として生き抜くスキルを磨け
この対談から見えてくるのは、私たちがもはや「国や会社がなんとかしてくれる」という幻想を抱いてはいけない、という厳しい現実です。
世界はより複雑で、予測困難な時代に突入しました。そして、日本の相対的な経済力は、残念ながら低下していく可能性が高い。
そんな未来に向けて、私たちが個人として備えるべきこと。 それは、特定の組織に依存しなくても生きていける「個の力」を磨くことに他なりません。
それは、専門的なスキルかもしれませんし、ひろゆきさんが一貫して主張するように、「お金をかけずに豊かに生きる生活術」かもしれません。
どんな時代、どんな環境の変化にも対応できる「サバイバル能力」こそが、これからの未来を生き抜くための、最強の武器となるのです。
まとめ
今回は、ひろゆきさんが高橋弘樹さんと語り合った、人生における「お金と時間の最適化」についての議論をご紹介しました。彼の言葉は、時に過激に聞こえるかもしれませんが、その根底には、社会の常識や他人の価値観に振り回されず、「自分自身の幸福を最大化する」という、極めてシンプルで一貫した哲学があります。
あなたが、より自由に、より幸せに生きるための「ひろゆき流・人生のOS」、4つの基本原則を振り返りましょう。
- 家は「買う」な。「借りろ」
- 資産価値が下がり続ける日本の家は、負債である。地理的な自由と、ライフステージに合わせ変化できる身軽さを最優先せよ。
- 結婚は「制度」と割り切れ
- 万人にとっての幸福の形ではない。人間関係の本質を見極め、自分たちに合った、より合理的なパートナーシップを模索せよ。
- 幸福度は「基準値を下げて」最大化する
- 大きな成功体験ではなく、「今日の卵かけご飯がうまい」で喜べる感性こそが、持続可能な幸福の源泉である。
- 収入ではなく「自由な時間」を最大化せよ
- 生活費を稼いだら、それ以上のお金のために時間を切り売りするな。投資(NISAなど)で不労所得の土台を築き、人生で最も貴重な資産である「時間」を買い戻せ。
彼の考え方すべてに同意する必要はありません。しかし、一度立ち止まり、社会があなたに押し付ける「当たり前」を疑ってみること。それこそが、あなただけの「人生の最適解」を見つけ出す、最も重要な第一歩となるはずです。